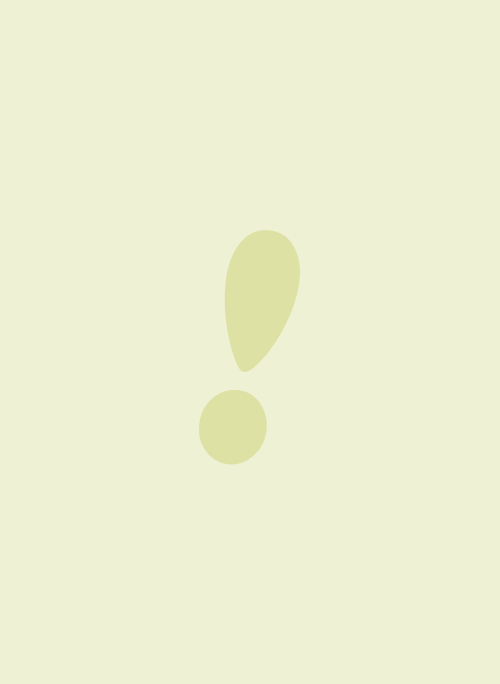そのパニックから救いだしてくれたのが、スキー場から流れるアナウス、新年を告げるカウントダウンだった。
店内はたちまちにガラガラになり、ドアはあっけぱなしに、注文だけしていなくなる客もいた。
それもそのはず、今日、この時間にスキー場に来ている客のほとんどが、今から始まる、ミレニアムイベントのために来ているのだから。
店長がぼくら、バイトのメンバーを見て言った。
「それじゃ、僕たちも外に少しでてみますか」
朝から休みなく、働いていたメンバーの顔が少し微笑みを取り戻した。
その中に、俺には特別なゆみの姿もある。
そしてカウントダウンも残すところ五秒前、スキー場に来ているすべての人が一体になった。
店内はたちまちにガラガラになり、ドアはあっけぱなしに、注文だけしていなくなる客もいた。
それもそのはず、今日、この時間にスキー場に来ている客のほとんどが、今から始まる、ミレニアムイベントのために来ているのだから。
店長がぼくら、バイトのメンバーを見て言った。
「それじゃ、僕たちも外に少しでてみますか」
朝から休みなく、働いていたメンバーの顔が少し微笑みを取り戻した。
その中に、俺には特別なゆみの姿もある。
そしてカウントダウンも残すところ五秒前、スキー場に来ているすべての人が一体になった。