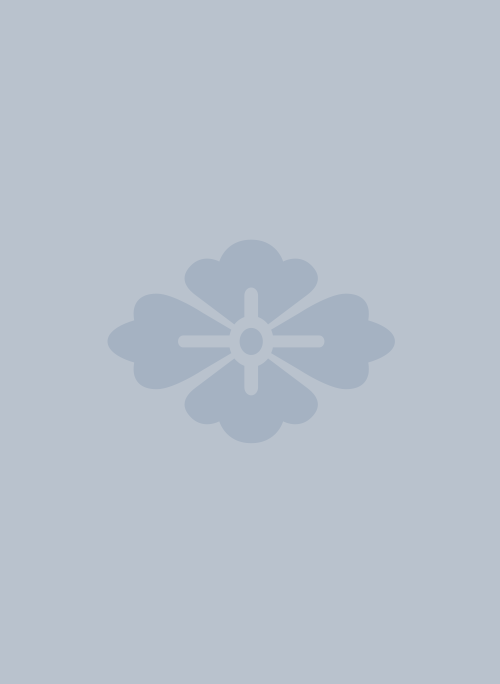だけど、今はまだ気付いていないふりをしていたくて。
誰にもそれを言わずにいる。
とりあえず上がればと神崎くんに声をかければ、彼は嬉しそうに頷いていそいそと靴を脱ぎ始めた。
まるで尻尾を振る犬のようだと思ったのは秘密である。
「あ、そういえば。また来てましたよ。あの黒い封筒」
俺と一緒にリビングまで歩いてきた彼が、ふと思い出したように顔を上げてそう言った。
その言葉に俺は机の上に置いた箱をちらりと見ながら一枚の封筒を思い浮かべる。
ある、一枚の封筒を。
そして同時に、彼を部屋に上がるよう促したことを猛烈に後悔した。
「…あぁ。いつものな」
それを悟られないよう俺は声のトーンを変えずに彼に返事を返す。