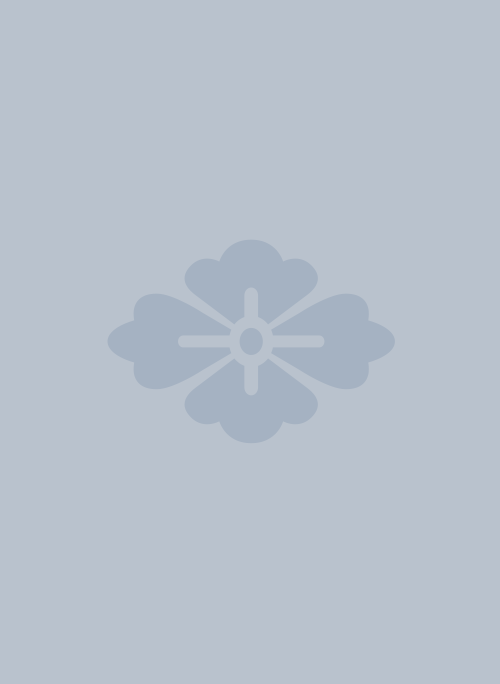「なんだ。まだ書けてなかったの?もう三日も経ってるじゃん」
そしてまだ一文字たりとも書けていないそれを見て、呆れたような溜め息を吐いた絢子。
何やってんのよ言いたげな彼女に、私は体を縮ませながら小さく頷くのだった。
目の前には白紙の便箋。
改めて握ったペンだって動く気配を見せない。
「だって…なに書けばいいかわかんなくて…」
やっぱり、それが本音だ。
そもそも普段手紙なんて書かないのだ。
私のコミュニケーションツールの一環に、手紙を書くという行動自体存在しない。
手紙の書き出しなんて当の昔に忘れてしまった。
それなのに突然好きな人に手紙を書け、だなんて。難易度が高すぎる。
「どこが好きですーとかでいいんじゃないの?」