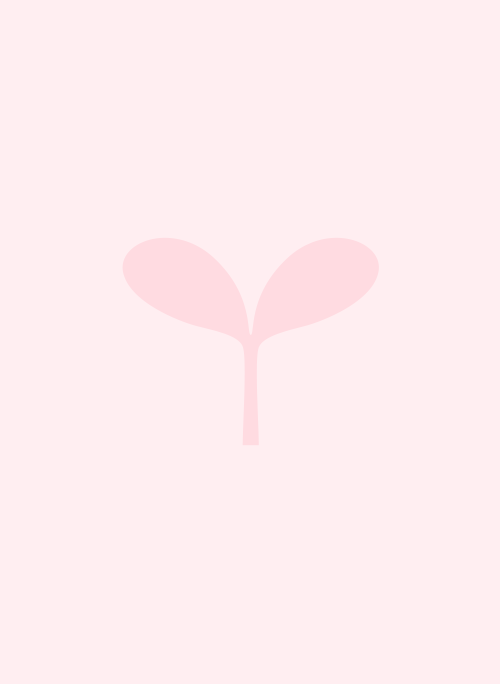15本目の道を曲がると、賑やかな市場が見えて来た。
ラザクは無事路地を抜けた事にほっとして、行き交う人々を観察する。
手には各々買い物袋をぶらせげ、朝食時だからだろうか、何かを食べながら市場を歩いている人が多かった。
ラザクも何か美味しそうなものがあったら買おうと、道沿いに連なっている店を確認していく。
あれからずっとタザの話しは続いていたが、ラザクは完全に聞き流していた。
「俺の親父、砂運びの仕事をしているだろ?
俺も小さい頃からよく手伝わされていたけど、国の周りの砂をひたすら運ぶだけの地味な仕事なんだ。
俺、そんな仕事に就くことになったら、発狂して死んじまう。」
「うん、そうだね。」
もちろん、相槌は適当に打つ。
そんな中、大好物の干し芋を焼き売りしている店を発見した。
タザの話が途中であったが、迷わず駆けて行って注文する。
「干し芋一つ下さい!」
「はいよ、"5サン"ね。」
鞄の中から財布を取り出し、言われた額を支払うと、干し芋が手渡された。
少し炙っているのか、受け取ったものは熱く、焦げ目がついている。
良い匂いだ。
早速頂こうとしたラザクの肩をタザが掴む。
「おい、ラザク。お前人の話聞いてんのか?」
ラザクはきょとん、とした顔で答えた。
「え、タザも食べるのか?」
「……。」
無言のタザから拳が飛んで来る。
ラザクはそれを難なくかわすと、干し芋を頬張った。
やっぱり干し芋はうまい。
「ラザク、お前って奴は…俺が不安な胸の内を語っているというのに、まるで聞いていなかったんだな!」
タザはラザクに掴みかかり、干し芋を奪う。
そして一口食べると、奪ったものをラザクに返し、自分の分を注文するため先程の店へと走って行った。
「なかなか美味いな、これ。」
口いっぱいに干し芋を頬張りながら戻ってきたタザは、満足そうだ。
「だろ?俺、今日の朝飯満足に食えてないから、大好物を見たら我慢出来なくてさ。
それ食べて悩みなんか忘れようぜ!」
ラザクは満面の笑みをみせた。
つられてタザも笑顔になる。
18年間共に過ごしてきた幼馴染の扱い方を、ラザクはよく心得ていた。