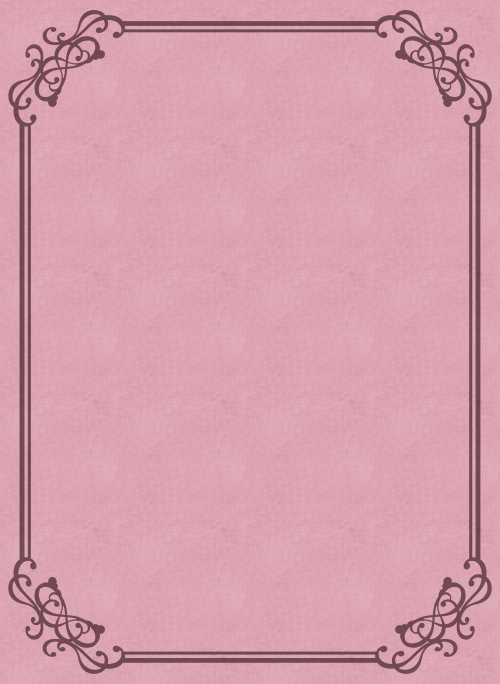各テーブルの席に番号を書いた付箋を貼り付けていって、チラシを箱型に折るとその中に同じく番号を書いた紙を折って入れていく。
作り終えたちょうどその時にガラガラと扉が開いて、女将さんの「らっしゃい」という掛け声に顔を上げる。
「おお、早いなあ、幹事は」
「お疲れ様です。クジ引いてってください」
そこに現れたのは須藤先輩とその他数名の同僚だ。
ぞろぞろと私のいる場所にやって来るとクジを引いて各々座っていく。
けれど須藤先輩だけは私の隣にドカッと座って、まじまじと顔を見つめてくる。
意識して軽口を叩こうと口を開いた。
「やっぱり可愛いですか、私」
「お前よく自分で言えるなあ。可愛いけどな」
そう言われて笑いあって、少し元気が出た。
須藤先輩は短い髪をさらにゴムで結い上げながら、「で?」と声をかけてくる。
「……何かあったか?目、赤いぞ、コノヤロウ」
ーーこの先輩が変人と呼ばれながらも皆に好かれていて、長く続く彼氏がいるのも、きっとよく周りを見ているからだと知っている。
「……今さら、須藤先輩とか女豹の言葉が身にしみてます」
「と、いうと?」