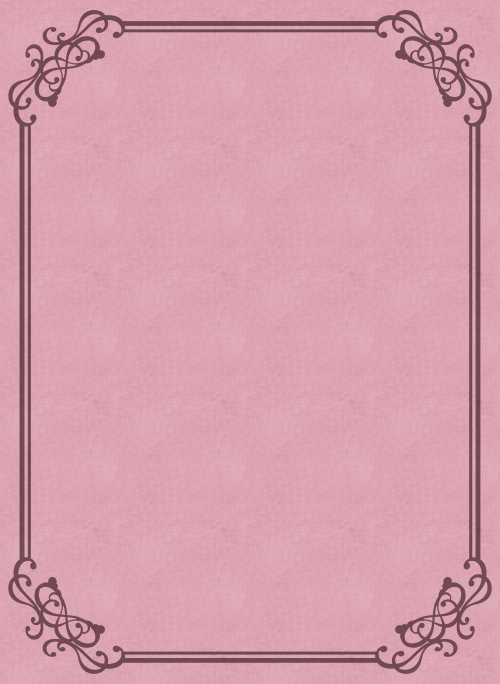「三時半ですね。
中途半端な時間ですし、帰ろうかな」
「そう?
じゃあ、駅まで送るよ」
「えっ、そんな。
悪いですよ。ここで大丈夫です」
「いいよ。俺はこの近所に住んでるから歩いて帰れるし…。
それに、帰ってもやることあるわけじゃないしさ」
そこまで言われると、じゃあ、もう少し一緒にいても良いのかな、なんて考えて嬉しくなる。
「じゃあ、お言葉に甘えて…」
「うん。
えっと、駅はこっちだよ。おいで」
そう言って、ぽん、と背中を叩かれて
その温もりにふわっと胸が躍った。
先輩の後ろについて行きながら、さっきふと思ったことが蘇る。
「そういえば、今日は香水つけてないんですね」
「ん?ああ、うん。よく気付いたね」
そして彼は、悪戯っぽく笑う。
「オフの時はつけないよ。
あれは会社への俺なりの武装だからさ」
「女子で言う所の化粧みたいな感じですか」
「そうなのかな。
自分に自信がないことの表れ、なのかもね。
香水つけて、自分はデキる!って毎日思い込んで出社するのが、新入時代からの毎朝の儀式みたいになってる」
(あ……)
先輩は、仕事がデキるひとだ。
実際にそれは事実なんだけど、勝手にそれは先輩の天性の才能か何かだと思っていた。
でも、違うのかもしれない。
先輩にも私みたいに新米だった時があって、きっと悩んで、失敗していた頃があるんだ。
今さらそんな当たり前のことに気付く。
そして今もまだその儀式が続いているということは、先輩は自分の仕事に決して満足しているわけではないんだ。