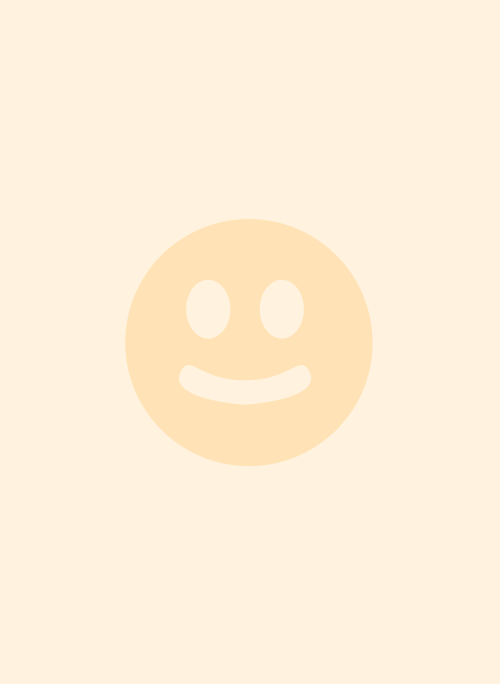次の日、各々勉強道具を持参していつものファミレス前に集合した。なんでも、まどかの家はここからすぐ近くらしいのだ。
「いざ参る。」
「いや直江のテンション誰かどうにかして。」
「香奈子、呼ばれてるぞ。」
「かな、出番だよ。」
「いやなんでやねん。」
そんないつも通りなあたしたちの中、まどかだけはどこか元気がない。やはり無理に突入するのは良くなかったか…
「直くん、人様のお家ではくれぐれも大人しくするんだよ。それが守れないのならば直くんはお家でお留守番だからね。」
「がんばります。」
「もはや母親と小学生の会話だな。」
「直江くんの精神年齢は小学生と同等だと思ってる。」
「せめて6年生でお願いします。」
「小学生なことに反論はないんだな…」
ぞろぞろと歩きながらまどかの家に向かう。先頭にまどかとあたし、後方にメグ、まん中が直くんとさぁちゃんだ。
「まどか、ここまで来ちゃってもう遅いかもだけどさ、本当に来ても大丈夫だったの?お母さん、いるんでしょ?」
直くんが自販機に目を奪われてまん中以降が切り離されたときに小さな声でまどかに尋ねた。
「うーん、どうだろうね…人を家に連れてくの初めてだから、どうなるかあたしにもわからんわ。」
「そっか…ごめんね。」
「なにが?」
「だって、あんまり来てほしくなさそうだったじゃんか。」
「まぁ、ね。でもかーちゃんたちなら大丈夫だと思うよ?さすがに高校生に交友関係までは口出ししてこないでしょ。なんか言って来たらあんな家出てってやるし。あ、もしそうなったらかーちゃんの家にお邪魔するかもな。」
そんなことを言ってカラカラ笑うまどかだが、その目はやっぱり笑っていなかった。