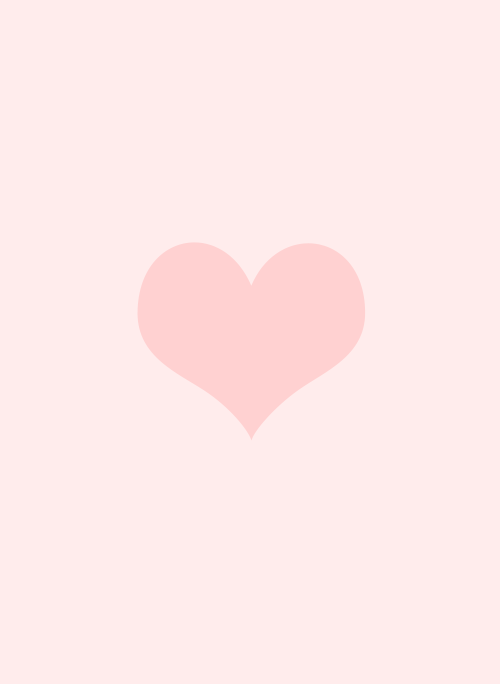「フランちゃん・・僕たちが男なのわかっていってる?」
「君結構セクシーだよね・・?」
「セ・セ・・・とやらはなんだ?」
鸞は私の耳元に顔を寄せると・・
「妖艶ってことだよ」
「きっきゃあああああ!」
「何興奮してんだ?そんなにやりたいのか?」
「変態スケベ!」
にしてもフランって「胸でかいな!」
「おーまえらぁぁぁ!殺す!」
「はいはいはい子供みたいなこと言わないの!」
珍しく魁がおさめる。
「フランちゃん許して?chu」
「きききききき・・」
私のほっぺにキスをした。
かぁぁぁぁあぁ
「かわぃーフランちゃん」
はっ
すっかりこいつらの言うことを真にしていたらだめだ。
こいつらを目が届くところに保護しとかないと信用できん。
「そんなこと思ってない癖に口にするな。」
「・・。」
「お前ら、良いかわからないがとりあえず母と相談したいことがある。縄をほどいてくれ。」
「えーダメ。」
「・・・。」
「なんでだぁぁぁぁぁぁ。」
「お前が母親に俺らのことを話すと俺らが捕まる可能性も少なくないからだ。」
「それはありえないわ。うちの母はそんなことしたことないもの。たとえ食い逃げした人だろうが何かしらの理由があるからといい警護の奴らに売ったりなんてしない。」
「・・じゃあ交換要件にしない?」
「条件によるわ。」
「もしお前の母親が俺らのことを知ったとき怖がるふりをしたら・・
直ちにお前をさらってここに戻る。」
「わかった。」
「そ、即答・・・」
「だって私は母を信じているから。」
そう、
それはこれからおこる余興とも知らずに私たちは出会ってしまったのだった。
「君結構セクシーだよね・・?」
「セ・セ・・・とやらはなんだ?」
鸞は私の耳元に顔を寄せると・・
「妖艶ってことだよ」
「きっきゃあああああ!」
「何興奮してんだ?そんなにやりたいのか?」
「変態スケベ!」
にしてもフランって「胸でかいな!」
「おーまえらぁぁぁ!殺す!」
「はいはいはい子供みたいなこと言わないの!」
珍しく魁がおさめる。
「フランちゃん許して?chu」
「きききききき・・」
私のほっぺにキスをした。
かぁぁぁぁあぁ
「かわぃーフランちゃん」
はっ
すっかりこいつらの言うことを真にしていたらだめだ。
こいつらを目が届くところに保護しとかないと信用できん。
「そんなこと思ってない癖に口にするな。」
「・・。」
「お前ら、良いかわからないがとりあえず母と相談したいことがある。縄をほどいてくれ。」
「えーダメ。」
「・・・。」
「なんでだぁぁぁぁぁぁ。」
「お前が母親に俺らのことを話すと俺らが捕まる可能性も少なくないからだ。」
「それはありえないわ。うちの母はそんなことしたことないもの。たとえ食い逃げした人だろうが何かしらの理由があるからといい警護の奴らに売ったりなんてしない。」
「・・じゃあ交換要件にしない?」
「条件によるわ。」
「もしお前の母親が俺らのことを知ったとき怖がるふりをしたら・・
直ちにお前をさらってここに戻る。」
「わかった。」
「そ、即答・・・」
「だって私は母を信じているから。」
そう、
それはこれからおこる余興とも知らずに私たちは出会ってしまったのだった。