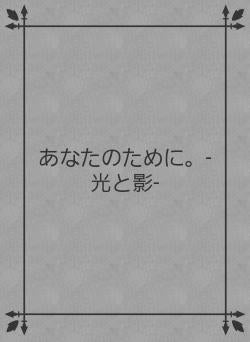無理やり聞くことだけはしたくない。
傍にいれば、いつか話してくれる奴らだって信じてるから。
武井が俺に話を聞いて欲しいとしても、武井が話すまで俺はいつまでも待つ。
いつまでも待ってしまうほど、俺はこいつらが大切なんだ。
いつからだろうな、こいつらを大切だと思うようになったのは。
「……あたしはあいつらとは違って、元々両親がいないんだ。
産まれてすぐ、段ボールに入れられて捨てられた」
「…え?」
武井がいきなり話し出すから驚いてしまった。
武井は空を見上げ、自嘲の笑みを浮かべている。
「…あいつらとは両親がいないのは同じだけど、あいつらは両親の顔を知ってる。
両親と一緒に撮った写真だって持ってる。
でもあたしは両親の顔も知らないし、両親との写真もない。
家族というものを知ってるあいつらが羨ましかった」
武井は徳永と時田を優しい瞳で見ている。
徳永が武井の目線に気付き、手を振っている。
「花織はアンタのことを優しかった父のようだと言ってた。
早苗は母方に引き取られた兄のようだと言った。
でもあたしはそう言われても分からない。
家族なんて元からいなかったし。
なぁ、家族ってなんだ?」
この世に絶望していた武井の目が、悲しみを帯びた。
今にも泣きそうだ。
寂しいんだよな?
家族が欲しかったんだよな?
俺が言えるのは……