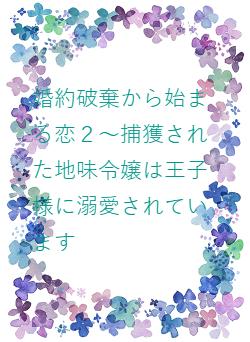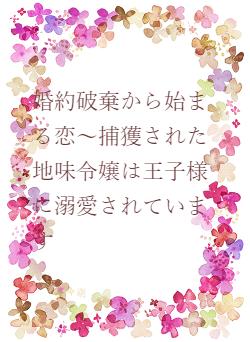声をかけた俺は、陽菜の目の前に立った。
「一緒に帰ろ」
「えっ」
って、びっくりしたように、2、3度目を瞬かせて、俺を見た。
「1人じゃ危ないよ。家まで送る。帰り道、同じ方向なんだ」
うそは言っていない。自宅は反対方向だけどね。
「そうなの?」
俺の言葉に安心したのか、彼女は一緒に帰ってくれた。
俺たちは並んで歩き出す。
歩き出したは、いいけれど、沈黙の時間が続く。
「一緒に帰ろ」
「えっ」
って、びっくりしたように、2、3度目を瞬かせて、俺を見た。
「1人じゃ危ないよ。家まで送る。帰り道、同じ方向なんだ」
うそは言っていない。自宅は反対方向だけどね。
「そうなの?」
俺の言葉に安心したのか、彼女は一緒に帰ってくれた。
俺たちは並んで歩き出す。
歩き出したは、いいけれど、沈黙の時間が続く。