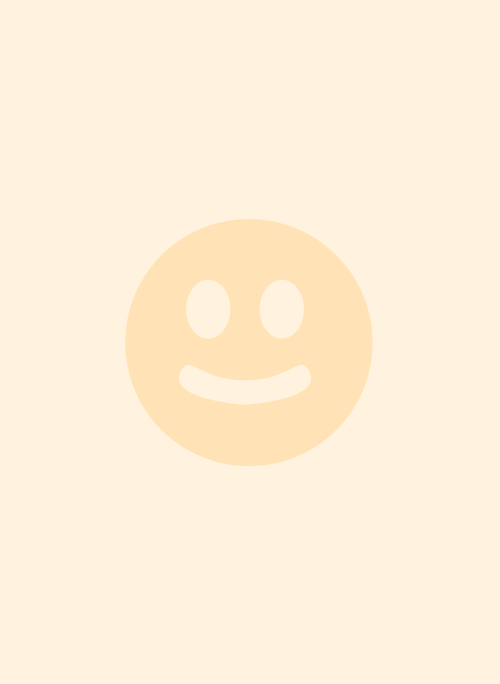「別に、許したわけじゃないからね? これはお礼だから」
「わかってます、ありがとうございます!」
「もう、声が大きい。子供が起きちゃうでしょ」
「あっ、すいません!」
「もう・・・ 本当にありがとね。じゃまた会社でね、剛彦」
「剛彦・・・?」
「もう、早く帰りな!」
芳美は頬を赤くしながら、剛彦の体を玄関の外へと押し出した。
「あっ、はい! おやすみなさい!」
芳美は帰って行く剛彦の背中を、見えなくなるまでずっと見送っていた。
「剛彦・・・ 芳美さんが俺の名前を呼んでくれた・・・ やったぁぁぁー!」
剛彦は沈む夕日の下、飛び跳ねながら帰って行った。
「わかってます、ありがとうございます!」
「もう、声が大きい。子供が起きちゃうでしょ」
「あっ、すいません!」
「もう・・・ 本当にありがとね。じゃまた会社でね、剛彦」
「剛彦・・・?」
「もう、早く帰りな!」
芳美は頬を赤くしながら、剛彦の体を玄関の外へと押し出した。
「あっ、はい! おやすみなさい!」
芳美は帰って行く剛彦の背中を、見えなくなるまでずっと見送っていた。
「剛彦・・・ 芳美さんが俺の名前を呼んでくれた・・・ やったぁぁぁー!」
剛彦は沈む夕日の下、飛び跳ねながら帰って行った。