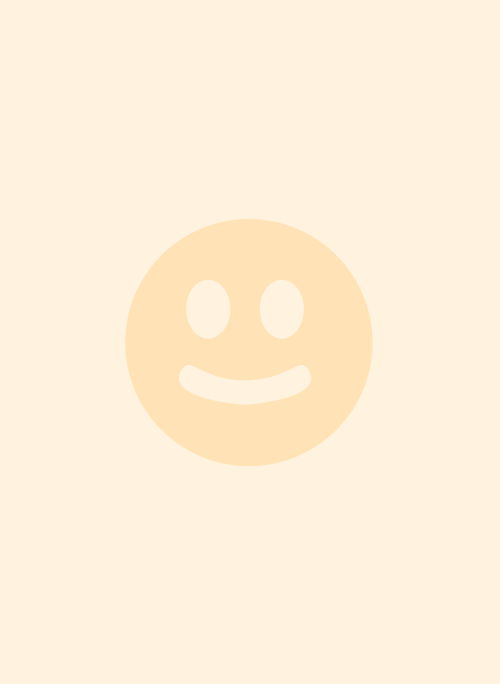「何か、いやなことでも、あったの?」
聞いてはいけない。
そんな気がした。
でも、好奇心に負けてしまって、ついそんな言葉を発してしまった。
「……。」
淨弥君は一瞬、寂しそうな顔をしたが、すぐに元の表情に戻った。
「寒くない?」
「え?あ、うん、少し」
「温めてあげる」
「………!!!」
淨弥君はあたしの手を引き、自分の胸にあたしの頭を優しく押し付けた。
「せ、淨弥君っ「シー…」
耳元で囁かれたその声に、ゾクッとした。
淨弥君の胸の中は、温かくて、洗剤のいい香りがした。
「……。」
ゴクッと唾を飲み、できるだけ平常心を保とうとした。
……が、
心臓はあたしの言うことなんて全く聞かず、
うるさく反応する。
「……あったかい…」
小さい声でそう言って、淨弥君はあたしを更に、強く抱きしめた。