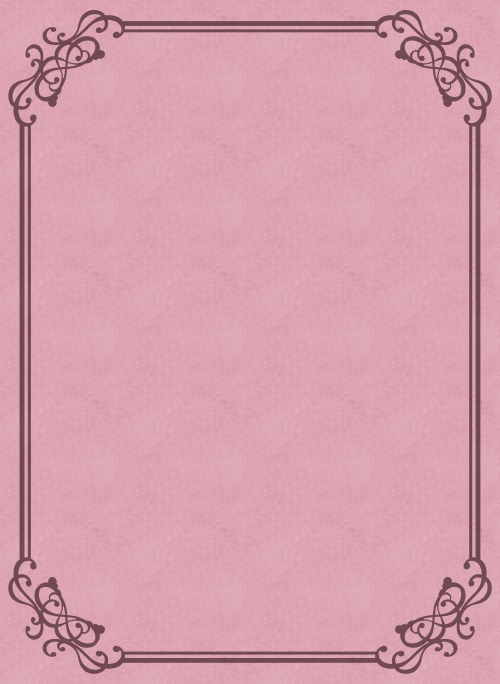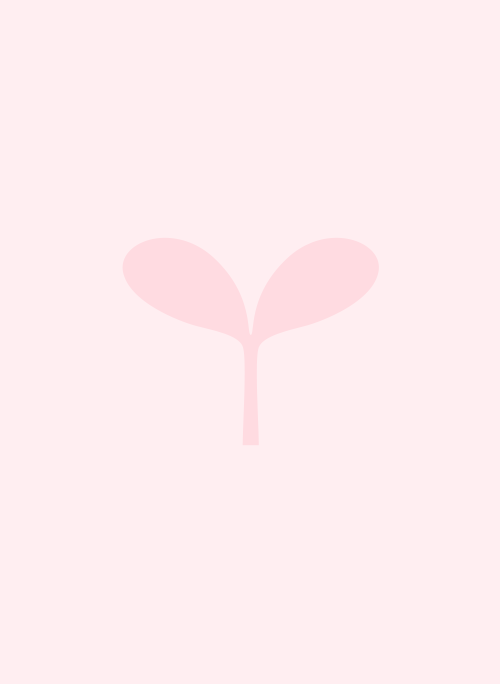階段を降りて、明かりが少ししか
点いていない廊下を歩いた。
地下だからなのか、冷たく、
じめじめしている。
しかもエルの創作料理と思わしきものの
臭いがする。
生ゴミと変わらないような臭いで、エルの料理のなかでも失敗作なものの様だった。
なんとも言えない、強いていうなら___
この世に存在する味や臭いに関しての
言葉を最大限活用するのなら、
甘ったるくて、とても苦い。
そんな臭いだ。
人類は、味に関しての言語はまだまだ
未開拓と言えよう。
私は初めてそう思った。
なるべく鼻で息をしないようにして、
私は廊下を歩いた。
すると、奥の部屋から情けない
男の叫び声が聞こえた。
部屋の位置について、“恐らく”が
“確信”に変わり、私は迷うことなく
その扉を開けた。
「お嬢様、食事なされるか
お部屋に避難されてりゃよかったのに」
エルが振り向いてそう言った。
(バカクィンテッドは喋らないか言葉遣いが悪いかのどちらかだが、中でもエルは
言葉遣いが非常に悪い。
今でもヴィル爺はそれにたいして注意しているが、正直、私はもう諦めている。)
その奥にはシリウスがいて、
蝋燭を持っていた。
明かりがその蝋燭しかないので、
とても暗い。
恐らくこれから壁にかけてある蝋燭にも
火をつけるんだろうが、私は今のままで
よかった。
なぜなら、真ん中にあったはずの
テーブルが移動させられ、そこに
叫んでいた男が捨てられていたからだ。
まだ“焼いている”段階のようで、
焦げてはいなかった。
暗いが、お腹を何発か殴られていて、
顔も醜く痣だらけなのがよくわかる。
これに蝋燭の淡い光が加われば、
汚いものをみることが確定していた。
「エル、私だって男に食事の邪魔さえ
されなければ、
今頃鶏肉を切っていたであろう
あのステーキナイフが男の足に
刺さることはなかったはずですよ」
「やっぱり一人取り逃がしてたか」