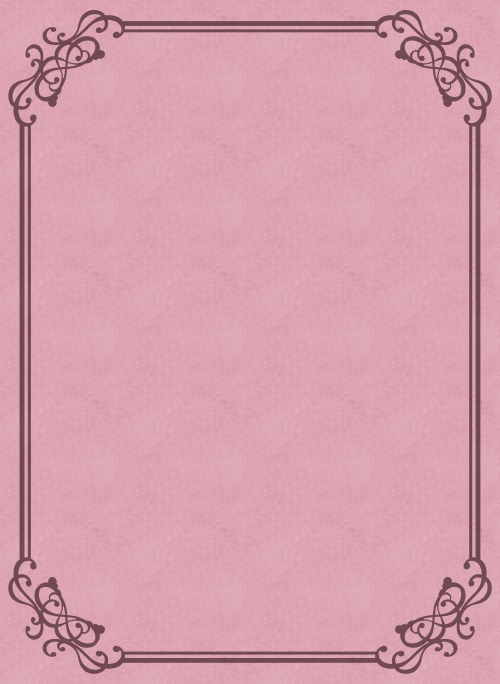前に言ったことがある。
忙しいでしょうから、カバリ様がわざわざこちらに来られなくても大丈夫ですよ、紅茶殿の者が王に直接要望を聞きに行きましょうか、と。
けれど彼はやはり真面目な顔をして、その黒髪をふるふると横に振るわせて、ほんの少しだけ微笑んで。
『この時間が俺の唯一の息抜きなのだ』
あの笑みが、ネルは忘れられなかった。
「……あ、の」
「ん?」
「煎じるのを見てるの、飽きませんか……?」
見られているのが恥ずかしくて、そんな可愛くないことを言ってしまう。
「いや、飽きることは無いな」
「そ、そうですか」
そうしてまた、朝の緩やかな時間が紅茶殿を満たした。
もう数百年前のことだというが、この国の三代目の王が大の紅茶好きだったことからこの紅茶殿という小さくも上品な佇まいの建物が城の片隅に作られた。
文官の役職の1つになるほど、この国の紅茶は特別だった。
香り、味、効能を選び取り、毎日王や国民のために煎じる。ネルはこの仕事が好きだった。
沸騰させたお湯を適温まで下げ、とぽとぽと煎じた茶葉に注いでいく。
透明だったお湯が、はちみつ色と枯れ葉色の間ーーまさに紅茶色に鮮やかに変化する。
「できました」
満足げに微笑んだネルに、カバリも頷く。
「ありがとう。そして……すまない」