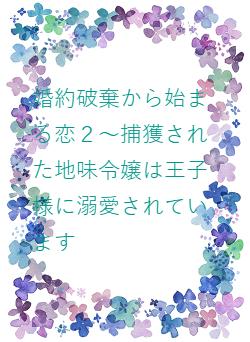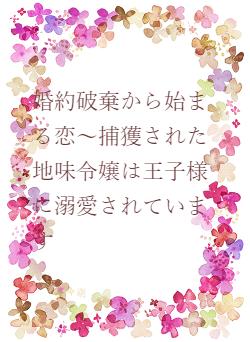もうすぐ日が暮れる。
わたしは緋色の家まで送ってきていた。
本当ならわたしの家はまだ手前で、
途中で別れてもおかしくはないのだけれど。
ちょっとの間でも心配で緋色を一人に出来ず、
いつも送り迎えをしている。
どうも気分は母親のようで・・・
目を離すと、何が起きるかわからない気持ちにさせられ、
はらはらする。
過保護だなという自覚はあるけど、緋色だからね。
そう思うのも仕方がないと思うのよ。
そろそろ帰ろうかと思っていた矢先、
その声は聞こえた。
「緋色」
幾分低い優しい声音。
聞き覚えのある声に振り向くと。
――――彼が立っていた。
わたしは緋色の家まで送ってきていた。
本当ならわたしの家はまだ手前で、
途中で別れてもおかしくはないのだけれど。
ちょっとの間でも心配で緋色を一人に出来ず、
いつも送り迎えをしている。
どうも気分は母親のようで・・・
目を離すと、何が起きるかわからない気持ちにさせられ、
はらはらする。
過保護だなという自覚はあるけど、緋色だからね。
そう思うのも仕方がないと思うのよ。
そろそろ帰ろうかと思っていた矢先、
その声は聞こえた。
「緋色」
幾分低い優しい声音。
聞き覚えのある声に振り向くと。
――――彼が立っていた。