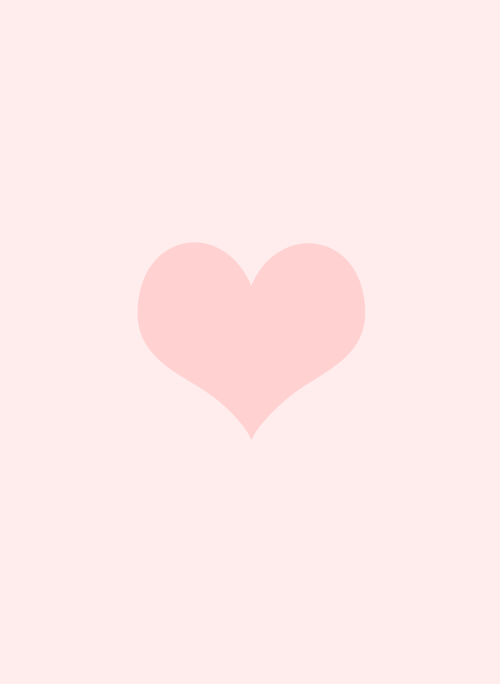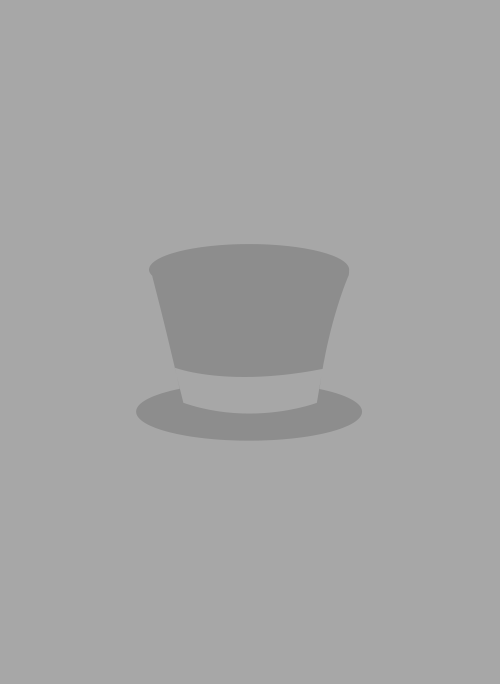「そう言う麗菜は、進路どうするんや?」
「あ?」
「進路はどうするんやて言うてるんや」
「俺は、大学行くんや」
「は?お前が?」
二人は校舎に向かって歩き始めた。
「せや!大学行く!かっこええやろ?」
「アホか。お前みたいなアホがどこの学校行けるんや?」
「ボケ。俺は、推薦や」
「あ、その手があったか」
麗菜は幼稚園の頃からずっとテニスをしていて、全国大会個人で2位の実績を持っているのだ。
「ええよなぁ、お前は。俺もテニスしとけばよかったわ」
頭を掻きながら誠が言う。
「アホか。誰にでも推薦来るわけちゃうわ。俺は優秀やからや!」
「あっそ」
「ほんで、お前はどうするねん?」
「あぁー…俺、どないしよかなぁ。全然考えてないねん…」
「まぁ、そんなことやろうと思っとったけど…でも、もう9月やぞ?そろそろ真剣に悩まな…」
「わかってるんやけど…。よっしゃ決めた、俺も大学行くわ!」
「はぁ?何や、急に?」
「大学行くって言うてるねん!」
「誠、お前本気で言うてるんか?何でいきなり大学やねん?」
「やりたいことないから、大学行って探すことにするわ!」
「何やねんそれ…ってゆうかもう9月やで?今から勉強したって無理やて」
「大丈夫やて、やれば何とかなるもんや!」
「むちゃくちゃやな…まぁ、頑張れよ」
と、麗菜が誠の肩をポンと叩く。
「あ?何やお前、俺ができへんと思てるんか?」
「当たり前やんけ」
「あ?ナメてんか?」
誠が麗菜の胸ぐらをつかむ。
「お、何や、やる気か?」
麗菜も誠の胸ぐらをつかんだ。
「上等やんけお前」
「何やコラ、かかってこいや!」
誠と麗菜は校舎の前で、大声を上げながら冗談半分の喧嘩を始めた。
「コラー!何やっとるか!」
そのとき、日光をよく反射しそうなハゲ頭の教師が走ってきた。
「ゲッ、教頭や…逃げるぞ、麗菜!」
二人は全力疾走で校舎の中に走って、急いで教室に入った。
「ボケ!俺、次喧嘩見つかったら退学や言うてるやんけ!」
「あ?」
「進路はどうするんやて言うてるんや」
「俺は、大学行くんや」
「は?お前が?」
二人は校舎に向かって歩き始めた。
「せや!大学行く!かっこええやろ?」
「アホか。お前みたいなアホがどこの学校行けるんや?」
「ボケ。俺は、推薦や」
「あ、その手があったか」
麗菜は幼稚園の頃からずっとテニスをしていて、全国大会個人で2位の実績を持っているのだ。
「ええよなぁ、お前は。俺もテニスしとけばよかったわ」
頭を掻きながら誠が言う。
「アホか。誰にでも推薦来るわけちゃうわ。俺は優秀やからや!」
「あっそ」
「ほんで、お前はどうするねん?」
「あぁー…俺、どないしよかなぁ。全然考えてないねん…」
「まぁ、そんなことやろうと思っとったけど…でも、もう9月やぞ?そろそろ真剣に悩まな…」
「わかってるんやけど…。よっしゃ決めた、俺も大学行くわ!」
「はぁ?何や、急に?」
「大学行くって言うてるねん!」
「誠、お前本気で言うてるんか?何でいきなり大学やねん?」
「やりたいことないから、大学行って探すことにするわ!」
「何やねんそれ…ってゆうかもう9月やで?今から勉強したって無理やて」
「大丈夫やて、やれば何とかなるもんや!」
「むちゃくちゃやな…まぁ、頑張れよ」
と、麗菜が誠の肩をポンと叩く。
「あ?何やお前、俺ができへんと思てるんか?」
「当たり前やんけ」
「あ?ナメてんか?」
誠が麗菜の胸ぐらをつかむ。
「お、何や、やる気か?」
麗菜も誠の胸ぐらをつかんだ。
「上等やんけお前」
「何やコラ、かかってこいや!」
誠と麗菜は校舎の前で、大声を上げながら冗談半分の喧嘩を始めた。
「コラー!何やっとるか!」
そのとき、日光をよく反射しそうなハゲ頭の教師が走ってきた。
「ゲッ、教頭や…逃げるぞ、麗菜!」
二人は全力疾走で校舎の中に走って、急いで教室に入った。
「ボケ!俺、次喧嘩見つかったら退学や言うてるやんけ!」