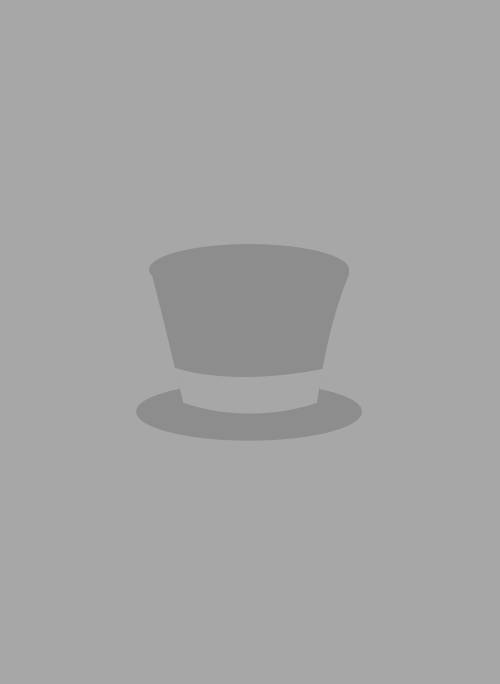微かなの音を奏でて、差し出されたコーヒーを、僕は受け取った。
「いただきます」
皿から小さなカップを、手に取り、僕は少し苦い香りを鼻で味わいながら、
カップに手をつけた。
「お、おいしい!」
香りとは裏腹に、苦くないコーヒーに感嘆した。甘くはないが…少しビターだ。
コーヒーをいれてくれたマスターは、僕の前で、満足気に頷き、
「宜しければ…おかわりがございますので……。いえ、お代は頂きません。実は、一杯目が、サービスなのですよ」
マスターは、にこりと微笑むと、早くもからになった僕のカップに、おかわりを注いだ。
そして、おもむろに、話出した。
「昔…高校野球の審判をしておりましてね。……いえ、甲子園ではございません。地方の予選の球場ですが…」
マスターの話は、こうだ。
ある決勝で、ホームベース。
滑り込んだ球児。
最終回だった。これが、最後だった。
一点入れば…同点で更に満塁だった。次は、絶好調の四番だった。
滑り込んだのは、ギリギリだった。
これで、甲子園が決まる、
しかし、あまりの砂ぼこりの煙て、グローブが邪魔して、あまり見えなかった。
アウト。
マスターの声が、こだましたとき、
負けた学校の夏は、終わった。
「今も、時々…夢を見ますよ。あの時の夢を…」
注ぎ終わったカップを、僕に差出し、
「本当に…アウトだったのかと…」
僕は、カップの中身を見つめた。
「だからね。審判をやめて、店を開く時に、決めたんですよ……もう間違えないと…」
僕は、カップに手をかけた。
「当店は、お客様の好みに合わせて、コーヒーをいれております。味が、合わなければ…いつでも、入れなおします」
僕はまた一口…啜った。
「だって…今は、お客様が審判なのですから…」
マスターは微笑んだ。
「いただきます」
皿から小さなカップを、手に取り、僕は少し苦い香りを鼻で味わいながら、
カップに手をつけた。
「お、おいしい!」
香りとは裏腹に、苦くないコーヒーに感嘆した。甘くはないが…少しビターだ。
コーヒーをいれてくれたマスターは、僕の前で、満足気に頷き、
「宜しければ…おかわりがございますので……。いえ、お代は頂きません。実は、一杯目が、サービスなのですよ」
マスターは、にこりと微笑むと、早くもからになった僕のカップに、おかわりを注いだ。
そして、おもむろに、話出した。
「昔…高校野球の審判をしておりましてね。……いえ、甲子園ではございません。地方の予選の球場ですが…」
マスターの話は、こうだ。
ある決勝で、ホームベース。
滑り込んだ球児。
最終回だった。これが、最後だった。
一点入れば…同点で更に満塁だった。次は、絶好調の四番だった。
滑り込んだのは、ギリギリだった。
これで、甲子園が決まる、
しかし、あまりの砂ぼこりの煙て、グローブが邪魔して、あまり見えなかった。
アウト。
マスターの声が、こだましたとき、
負けた学校の夏は、終わった。
「今も、時々…夢を見ますよ。あの時の夢を…」
注ぎ終わったカップを、僕に差出し、
「本当に…アウトだったのかと…」
僕は、カップの中身を見つめた。
「だからね。審判をやめて、店を開く時に、決めたんですよ……もう間違えないと…」
僕は、カップに手をかけた。
「当店は、お客様の好みに合わせて、コーヒーをいれております。味が、合わなければ…いつでも、入れなおします」
僕はまた一口…啜った。
「だって…今は、お客様が審判なのですから…」
マスターは微笑んだ。