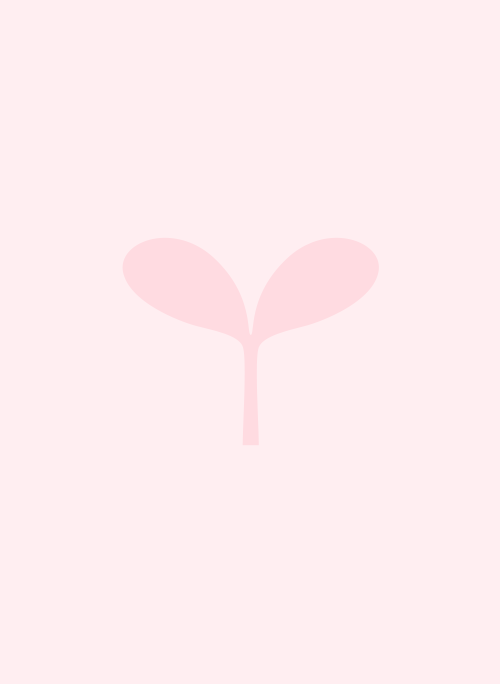多くの人が行き交う街中で、私は呆然と地面に投げつけられたモノを見つめる。
興味本位の視線があちらこちらから向けられるが、声をかけてくる者はいない。
明らかに通行の邪魔になっているというのに、そこだけぽっかりと穴が開いているかのように人々は避けていく。
険悪な雰囲気を漂わせる男女に、わざわざ首を突っ込んでくる野次馬がいないことだけは救いかもしれなかった。
「お前ってホント、センスもねぇし、つまんねー女。もう飽きたわ」
早起きして作ったお弁当が、彼に似合うと思って買ったシャツの上に転がっている。
蓋が外れて中身が零れたお弁当は見るも無残だし、地面に投げつけられたシャツも、土埃とおかずで散々な有様だった。
「じゃあな。今後連絡してくんなよ」
呆然と立ち竦む私にそれだけ言い残して、彼は背を向けた。
恐る恐る顔を上げて、歩み去る彼の背中を見つめる。
振り返る気配のない背中が徐々に小さくなって、やがて見えなくなった時、ようやく私の頭が動き始めた。
「あ、あつし君……」
絞り出した声はか細くて、見えない背中が戻ってくるはずもない。
のろのろとその場に膝をついて、汚れたシャツとお弁当を片付けた。
お弁当のおかずはシャツの上に収まっていたので、シャツでお弁当箱ごと包めば、地面は何事もなかったように元通りになった。
あとはシャツごとゴミ箱に捨ててしまえばいい。