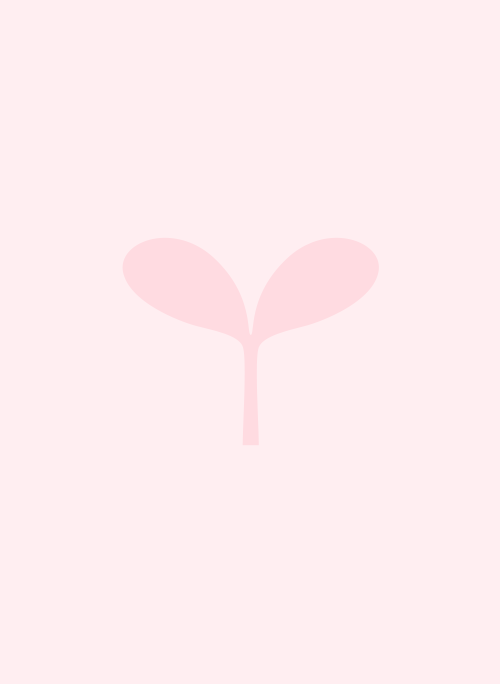「どうした、真っ青な顔をしておるぞ」
恵正は、朝食の支度をする富幸に声をかけた。いつか恵孝に言ったようなからかいはしない。
富幸は何でもないと首を振る。
「今日が、恵孝が進むべき道のりの最後の日だからね」
丹祢は富幸の背を撫でる。息子の嫁は、孫の母親は、あれからずっと気を張っている。張りすぎた糸は、いつ切れてしまうかわからない。せめてその心に寄り添うしかない。
「ご心配おかけして、申し訳ございません」
「いいんだよ。みんなで存分に心配しよう」
「そうじゃ」
義父母の言葉に、富幸はなんとか微笑みを浮かべた。飯と汁の椀を、食卓に並べる。
米を炊きながら、魚を焼きながら、野菜を切りながら、富幸は恵孝がきちんと食べているのかを気にしている。恵正と幼い頃から山を歩いてきた恵孝なら、食べられるものがあれば見つけるし、見分けて食べることは疑わないが、果たして見つけられているのか。飢えて倒れてはいないだろうか。城にいる恵弾は飢えることはないが、妙に気難しいところがある人だ。他の医師と共に、薬作りに励んでいるという様子が、今ひとつ思い浮かばない。励まない者が、無事でいられるのだろうか。「便りのないのは良い便りと心得よ」という手紙が城から届いて七日程経った。こちらからは手紙を送るが、恵弾からはその後何の便りもなかった。
「冷めないうちに、富幸も食べよう。お座りよ」
丹祢が声を掛けた。富幸は頷いて、椅子を引く。
恵正は、朝食の支度をする富幸に声をかけた。いつか恵孝に言ったようなからかいはしない。
富幸は何でもないと首を振る。
「今日が、恵孝が進むべき道のりの最後の日だからね」
丹祢は富幸の背を撫でる。息子の嫁は、孫の母親は、あれからずっと気を張っている。張りすぎた糸は、いつ切れてしまうかわからない。せめてその心に寄り添うしかない。
「ご心配おかけして、申し訳ございません」
「いいんだよ。みんなで存分に心配しよう」
「そうじゃ」
義父母の言葉に、富幸はなんとか微笑みを浮かべた。飯と汁の椀を、食卓に並べる。
米を炊きながら、魚を焼きながら、野菜を切りながら、富幸は恵孝がきちんと食べているのかを気にしている。恵正と幼い頃から山を歩いてきた恵孝なら、食べられるものがあれば見つけるし、見分けて食べることは疑わないが、果たして見つけられているのか。飢えて倒れてはいないだろうか。城にいる恵弾は飢えることはないが、妙に気難しいところがある人だ。他の医師と共に、薬作りに励んでいるという様子が、今ひとつ思い浮かばない。励まない者が、無事でいられるのだろうか。「便りのないのは良い便りと心得よ」という手紙が城から届いて七日程経った。こちらからは手紙を送るが、恵弾からはその後何の便りもなかった。
「冷めないうちに、富幸も食べよう。お座りよ」
丹祢が声を掛けた。富幸は頷いて、椅子を引く。