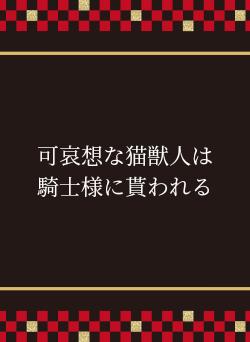──はーい猫ちゃん、元気?
良いお知らせよ。治療薬の材料がラッキーなことにドッザの露店で売られてたわ。予定よりだいぶ早く仕上がりそうよ。
この手紙が届く頃には完成してるかもね。あと少しだけ我慢してちょうだい。
体が戻ったら存分に猫ちゃんのすべすべお肌を撫でさせてもらうから身も心もちゃんと覚悟──
「何て素晴らしいタイミングなのでしょうっ! ツイていますわね私たち!」
カルミネ様から届いたお手紙を前半まで読み終え、私は思わず万歳をして飛び跳ねました。
第二王子派の貴族を順調に黙らせている最中に、更なる僥倖ですわ! このまま私とヴァルト様がお互いを演じ切ってしまえば、何事もなく元の体に戻れます!
そして──待ちに待った立太子の儀を迎えられますのね!
ああ、ここまで長かったですわ。一時期はどうなることかと思いましたけれど、幸運の女神は我々を見捨ててはいなかったのですね……! 順調すぎて怖いぐらいです!
「ところでセイラム様、このお手紙はいつ頃届いたのでしょう?」
「……カルミネ様は毎回、あの変な鳥に手紙を預けますから、気付いたら書類に紛れ込んでいることが殆どです。少なくとも今日か、昨日でしょうかね」
変な鳥? もしかしてカルミネ様も御伽噺に出てくるような呪術師らしく、使役しているカラスでもいるのでしょうか。それともコウモリ? フクロウも有り得そうですわね。
うっかりいろいろと想像してしまいましたが、とにかくその鳥さんによって、人の手を介さずにお手紙が届けられるそうです。凄いですわ、これなら誰にも治療薬のことは漏れていませんわね。
「……? ローレント嬢、もう一枚入ってないか」
「え? あら本当」
お着替えを済ませて執務室に戻ってきたヴァルト様が、私の手元を指差しては首を傾げました。促されて封筒の中を見てみれば、確かにもう一枚だけ文が添えられています。
「なになに……」
──もしかしたら次の仕事で予定が立て込むかもしれないの。悪いけど、その時は相棒に治療薬を配達してもらうわ。
取扱いに注意してね。
私とヴァルト様が思わず同じ方向に首を傾げていると、暫くしてセイラム様がどこか苦々しいお顔で舌を打ちました。
「相棒……まさかあの鳥に……」
「え、今仰っていた?」
「いいえ、手紙専用の鳥ともう一匹いるんです。ヴァルト様、お忘れですか。あれです、あの馬鹿鳥に持たせるつもりですよ」
側近から必死の様相で肩を揺すられながら、ヴァルト様は虚空を見詰めて記憶を遡っているようでした。
やがてはっきりと鳥さんの姿を思い出したのか、片方の眉がひくりと跳ねました。
「……ああ、あれか」
お二人共、カルミネ様の相棒兼配達係の鳥さんのことをご存じのようです。何でしょう、あまり良い印象を持たれていないようですけれど。
「──ヴァルト殿下、失礼いたします!」
執務室の扉が勢いよく開かれ、文字通り転がり込んできたのは小柄な少年──クロムでした。
天使のような笑顔を浮かべる彼が、セイラム様からは「優秀なクソガキ」と罵られ、ヴァルト様からは「過去に何か悲惨な経験でもしてそう(意訳:性格が歪んでいる)」などと散々な評価をされていると知ったときは頭が痛くなりました。
私もしれっとおちょくられた一人なので、これからは油断しないようにいたしますけれど。
「どうしたのです、クロム」
「あの、僕あれ初めて見たからよく分からないんですが、ええとー……」
あら? 珍しくクロムの歯切れが悪いですわ。というよりも随分と戸惑っているようです。
クロムはその場で足踏みをしながら、「とにかく」と王宮の外を指差しました。
「でかい鳥が門前に鎮座してるんです! ちょっと騒ぎになってまして、どう対処したものか判断しかねてます」
「鳥!」
私とヴァルト様はハッと顔を見合わせ、急いで部屋を飛び出しました。まさかこんなにも早くカルミネ様の治療薬が届くなんて、と喜びを覚える一方で、何故だか嫌な予感が胸に広がります。
勝手に退いてくれる人混みを駆け抜けながら、私は隣を走るヴァルト様に小声で訴えました。
「ヴァルト様、ここ最近何においても事が上手く運び過ぎて、何だか今から不幸が見舞いそうな気がしてなりませんの」
「そうだな、同感だ」
「え!? 気休めでも大丈夫と仰ってくださいませんこと!?」
「いや、それが……カルミネの相棒は少し──」
そのときヴァルト様の爪先がつんのめり、咄嗟に私は華奢な体を支えます。よく見たらヴァルト様、踵のある靴で全力疾走しているではありませんの!?
「ああもうっ私の足が壊れてしまいますわっ、ちょっと失礼しますわよ」
私は軽々とヴァルト様を横抱きにして、階段を駆け下りました。半ば飛び降りるようにして階下へ到着した私は、そこで途方もない悲しみを感じて「うっ」と唸ります。
「お姫様抱っこは……される側が良かった……ッ!!」
「すまんな。俺もされる日が来るとは思わなかった」
「ずるいですわ私より先にお姫様抱っこデビューを果たすなんて」
「体が戻ったらいくらでもしてやる。拗ねるな」
「え──」
ぼんっと顔が熱くなってしまいましたが、走りながら私はすかさずヴァルト様に確かめたのでした。
「げ、げげげげ言質は取りましたわよ!! してくださいますのね!?」
「ん? ああ」
「いくらでも!?」
「そう言った」
「でも体が戻ったら」
──こんなふうに軽々しく言葉を交わすことも出来ないのに?
閊えた言葉は音にならず、私の喉元に留まりました。うろうろと視線を彷徨わせてしまうと、生まれ出た戸惑いを一蹴するかのように、ヴァルト様が小さく笑いました。
「……。何か礼でもしてくれるのか」
「えっ。あ! そ、そうですわね、それもありますわね! 私ったらヴァルト様に良くしていただいてばかりですし」
「そうか。楽しみにしておこう」
──私、面白いくらい顔が赤いと思うのですけれど。
何ですの今の!? そ、それはその、体が戻ってもお会いしてくれるということですの!? ひえっ、筋肉王子のくせして誘導が鮮やかすぎません!?
「うええーん! 嫌ですわこの人! 初々しい乙女の心を弄んで何が楽しいんですのぉ!?」
「ローレント嬢、そろそろ着くぞ。恐らく正門前に──」
私の悶々とした叫びを清々しく無視したヴァルト様は、外の眩しい光に目を眇めたのち、怪訝な表情をなさいました。
良いお知らせよ。治療薬の材料がラッキーなことにドッザの露店で売られてたわ。予定よりだいぶ早く仕上がりそうよ。
この手紙が届く頃には完成してるかもね。あと少しだけ我慢してちょうだい。
体が戻ったら存分に猫ちゃんのすべすべお肌を撫でさせてもらうから身も心もちゃんと覚悟──
「何て素晴らしいタイミングなのでしょうっ! ツイていますわね私たち!」
カルミネ様から届いたお手紙を前半まで読み終え、私は思わず万歳をして飛び跳ねました。
第二王子派の貴族を順調に黙らせている最中に、更なる僥倖ですわ! このまま私とヴァルト様がお互いを演じ切ってしまえば、何事もなく元の体に戻れます!
そして──待ちに待った立太子の儀を迎えられますのね!
ああ、ここまで長かったですわ。一時期はどうなることかと思いましたけれど、幸運の女神は我々を見捨ててはいなかったのですね……! 順調すぎて怖いぐらいです!
「ところでセイラム様、このお手紙はいつ頃届いたのでしょう?」
「……カルミネ様は毎回、あの変な鳥に手紙を預けますから、気付いたら書類に紛れ込んでいることが殆どです。少なくとも今日か、昨日でしょうかね」
変な鳥? もしかしてカルミネ様も御伽噺に出てくるような呪術師らしく、使役しているカラスでもいるのでしょうか。それともコウモリ? フクロウも有り得そうですわね。
うっかりいろいろと想像してしまいましたが、とにかくその鳥さんによって、人の手を介さずにお手紙が届けられるそうです。凄いですわ、これなら誰にも治療薬のことは漏れていませんわね。
「……? ローレント嬢、もう一枚入ってないか」
「え? あら本当」
お着替えを済ませて執務室に戻ってきたヴァルト様が、私の手元を指差しては首を傾げました。促されて封筒の中を見てみれば、確かにもう一枚だけ文が添えられています。
「なになに……」
──もしかしたら次の仕事で予定が立て込むかもしれないの。悪いけど、その時は相棒に治療薬を配達してもらうわ。
取扱いに注意してね。
私とヴァルト様が思わず同じ方向に首を傾げていると、暫くしてセイラム様がどこか苦々しいお顔で舌を打ちました。
「相棒……まさかあの鳥に……」
「え、今仰っていた?」
「いいえ、手紙専用の鳥ともう一匹いるんです。ヴァルト様、お忘れですか。あれです、あの馬鹿鳥に持たせるつもりですよ」
側近から必死の様相で肩を揺すられながら、ヴァルト様は虚空を見詰めて記憶を遡っているようでした。
やがてはっきりと鳥さんの姿を思い出したのか、片方の眉がひくりと跳ねました。
「……ああ、あれか」
お二人共、カルミネ様の相棒兼配達係の鳥さんのことをご存じのようです。何でしょう、あまり良い印象を持たれていないようですけれど。
「──ヴァルト殿下、失礼いたします!」
執務室の扉が勢いよく開かれ、文字通り転がり込んできたのは小柄な少年──クロムでした。
天使のような笑顔を浮かべる彼が、セイラム様からは「優秀なクソガキ」と罵られ、ヴァルト様からは「過去に何か悲惨な経験でもしてそう(意訳:性格が歪んでいる)」などと散々な評価をされていると知ったときは頭が痛くなりました。
私もしれっとおちょくられた一人なので、これからは油断しないようにいたしますけれど。
「どうしたのです、クロム」
「あの、僕あれ初めて見たからよく分からないんですが、ええとー……」
あら? 珍しくクロムの歯切れが悪いですわ。というよりも随分と戸惑っているようです。
クロムはその場で足踏みをしながら、「とにかく」と王宮の外を指差しました。
「でかい鳥が門前に鎮座してるんです! ちょっと騒ぎになってまして、どう対処したものか判断しかねてます」
「鳥!」
私とヴァルト様はハッと顔を見合わせ、急いで部屋を飛び出しました。まさかこんなにも早くカルミネ様の治療薬が届くなんて、と喜びを覚える一方で、何故だか嫌な予感が胸に広がります。
勝手に退いてくれる人混みを駆け抜けながら、私は隣を走るヴァルト様に小声で訴えました。
「ヴァルト様、ここ最近何においても事が上手く運び過ぎて、何だか今から不幸が見舞いそうな気がしてなりませんの」
「そうだな、同感だ」
「え!? 気休めでも大丈夫と仰ってくださいませんこと!?」
「いや、それが……カルミネの相棒は少し──」
そのときヴァルト様の爪先がつんのめり、咄嗟に私は華奢な体を支えます。よく見たらヴァルト様、踵のある靴で全力疾走しているではありませんの!?
「ああもうっ私の足が壊れてしまいますわっ、ちょっと失礼しますわよ」
私は軽々とヴァルト様を横抱きにして、階段を駆け下りました。半ば飛び降りるようにして階下へ到着した私は、そこで途方もない悲しみを感じて「うっ」と唸ります。
「お姫様抱っこは……される側が良かった……ッ!!」
「すまんな。俺もされる日が来るとは思わなかった」
「ずるいですわ私より先にお姫様抱っこデビューを果たすなんて」
「体が戻ったらいくらでもしてやる。拗ねるな」
「え──」
ぼんっと顔が熱くなってしまいましたが、走りながら私はすかさずヴァルト様に確かめたのでした。
「げ、げげげげ言質は取りましたわよ!! してくださいますのね!?」
「ん? ああ」
「いくらでも!?」
「そう言った」
「でも体が戻ったら」
──こんなふうに軽々しく言葉を交わすことも出来ないのに?
閊えた言葉は音にならず、私の喉元に留まりました。うろうろと視線を彷徨わせてしまうと、生まれ出た戸惑いを一蹴するかのように、ヴァルト様が小さく笑いました。
「……。何か礼でもしてくれるのか」
「えっ。あ! そ、そうですわね、それもありますわね! 私ったらヴァルト様に良くしていただいてばかりですし」
「そうか。楽しみにしておこう」
──私、面白いくらい顔が赤いと思うのですけれど。
何ですの今の!? そ、それはその、体が戻ってもお会いしてくれるということですの!? ひえっ、筋肉王子のくせして誘導が鮮やかすぎません!?
「うええーん! 嫌ですわこの人! 初々しい乙女の心を弄んで何が楽しいんですのぉ!?」
「ローレント嬢、そろそろ着くぞ。恐らく正門前に──」
私の悶々とした叫びを清々しく無視したヴァルト様は、外の眩しい光に目を眇めたのち、怪訝な表情をなさいました。