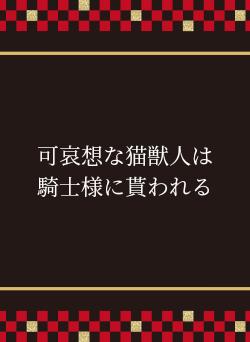「よろしいですねリシェル様。不本意でしょうが今現在あなたは男性であり、ヴァルト様であり、この国の王子です。出来るだけ堂々と振舞ってください」
「ど、堂々と……?」
着慣れないはずなのにしっくり来る衣服を撫でつけ、私は恐る恐るセイラム様に聞き返しました。
豪華な馬車の中、向かいに腰掛けたセイラム様は鷹揚に頷き、注意事項を指折り挙げていきます。
「えぇ。姿勢はそのままで構いませんが、手は体の横! 歩幅を大きく! 無い髪を弄ろうとしない! あとその座り方もいけません!」
「きゃあ!」
急に両膝を大きく開かれ、私はつい悲鳴を上げてしまいました。殿方の前でこんなはしたない格好をするなんて、もうお嫁に行けません。
などと思いましたが、よく考えたらドレスを着ているわけでもなし、紳士用の装いで股を閉じていると、かえって不自然に見えるとセイラム様は真っ青な顔で仰いました。
「……今のような野太い悲鳴もお控え願いたく存じます」
「やだ、ごめんなさい……」
「その言葉遣いもです。肩に力を入れない」
セイラム様はとても手厳しい御方のようです。
私は言われた通りに姿勢を伸ばし、脚を肩幅ほどに開き、両手を軽く握り込むようにして膝に置きました。座っているときは基本的にこの形を崩さなければ良いとのことです。
うぅ、私、これから両親の元へ行くと言うのに……。
──馬車が向かったのは、私の生家であるローレント伯爵邸でした。
つい先日まで過ごしていたはずの我が家が何処か遠く、他人の家のように感じてしまいます。
体の異変が判明するや否や、セイラム様が無理を通して外出を決めてくださったので、伯爵家への訪問通達はまだ届いていないかもしれません。いえ、もしかしたらそれどころではない可能性も──。
「ではリシェル様、先に私がローレント伯爵にお会いしてきます。間違ってもご両親に泣き付いたりしないでくださいね」
「は、はい」
「今のあなたは一国の王子。石の如く鎮座しているだけで構いませんから」
よほど私に対する信用がないのか、セイラム様は馬車から体を離しつつ何度も注意を促しました。そんなに大声を上げていたら屋敷にも聞こえてしまいそうです。大丈夫ですから早く行ってください、と窓から手を振れば、ようやく背を向けてくださいました。
ホッと息をついたのも束の間、誰もいなくなってしまった狭い空間に、私はすぐ心細くなりました。
馭者の方に話しかけられたらどうしましょう。セイラム様がいらっしゃらないと、きっとボロが出てしまいます。あぁ、どうし──。
「いやァァァァ!! リシェル、早く戻って来てちょうだい、お願いよぉ……!!」
悲痛な叫びが外から聞こえ、驚いた私は馬車の扉を蹴破ってしまいました。拉げた扉が草むらの向こうへ消える様を、私は唖然と見送りました。
この体はどうなっているのでしょう。手足が当たっただけで物が壊れてしまうのです、決して私のせいでは……いえ、今は言い訳をしている場合ではありません。
唐突に馬車が大破し青褪める馭者の方には目もくれず、私は急いで外へ飛び出しました。
──え?
か、軽い!
体が軽すぎる!
私、こんなに速く走れたのは人生で初めてです!
凄いですわ、ヴァルト様のお体はこんなにも大きいのに、どうしてこれほど俊敏に動けますの!?
「うおぉ!? ちょ、どちらへ行かれるんですかヴァルト様──」
どうしましょう!
走るのに夢中で、ついセイラム様を追い越してしまいました!
ですが止まれません、止まりたくないのです!
「この脚が動かなくなるまで!!」
「あんたは闘牛か!! 早急に止まれ!!」
「と、闘牛!? 酷いですわセイラム様……!」
セイラム様の発言に崩れ落ちた私でしたが、おかげでようやく我に返りました。ヴァルト様のお体が羽のように軽いからと、人目も憚らず爆走してしまうなんて。きっとこの体には恐ろしい興奮作用があるに違いありません。
おいおいと蹲る私に追いついたセイラム様は、肩で息をしながら険しいお顔でその場に屈みました。
「何ですか、あなたは鳥頭ですか? 先に私が伯爵にお会いしてくると言いましたよね……?」
「あぁぁ、ごめんなさいセイラム様。ですが母の悲鳴が聞こえて、思わず走り出してしまいました」
「悲鳴?」
「えっ、お聞きになりませんでしたか?」
まさか私の聞き違いだったのでしょうか。恥ずかしくて穴に入りたい気分です。この腕なら余裕で硬い地面も掘れてしまいそうですが。
コツコツと石畳を叩き始めた巨漢に危機感を覚えたのか、セイラム様は慌てて私を立ち上がらせました。
「ヴァルト様は耳も良いですから、聞き違いではないと思います」
「まあ……ヴァルト様は人間ではありませんの?」
「その姿じゃなければ不敬罪で処しているところですよ」
やっぱりセイラム様は怖い御方です。いえ、今のは明らかに私の失言でしたけれど。
それにしても、ヴァルト様に対してもこのような態度なのでしょうか。王太子となられる御方に向かってゴリラや闘牛だなんて、普通に考えればそれこそ不敬罪です。
もしかしたら古くからのご友人で、気の置けない仲なのかもしれません。殿方同士の友人関係がどのようなものなのかは存じ上げませんが、きっと砕けた間柄なのでしょう。
「──セイラムじゃないか。こんなところで何をしている」
そのとき、私とセイラム様の元へ小柄な女性が現れました。
長く嫋やかな銀髪を前髪ごと無造作に後ろで束ね、肩まで捲り上げたブラウスからは白い腕が剥き出しになっていました。
何てはしたない格好なのでしょう。ついつい眉を顰めましたが、次の瞬間に私は雄叫びを上げて少女を屋敷の中へ運び込んだのでした。
「ど、堂々と……?」
着慣れないはずなのにしっくり来る衣服を撫でつけ、私は恐る恐るセイラム様に聞き返しました。
豪華な馬車の中、向かいに腰掛けたセイラム様は鷹揚に頷き、注意事項を指折り挙げていきます。
「えぇ。姿勢はそのままで構いませんが、手は体の横! 歩幅を大きく! 無い髪を弄ろうとしない! あとその座り方もいけません!」
「きゃあ!」
急に両膝を大きく開かれ、私はつい悲鳴を上げてしまいました。殿方の前でこんなはしたない格好をするなんて、もうお嫁に行けません。
などと思いましたが、よく考えたらドレスを着ているわけでもなし、紳士用の装いで股を閉じていると、かえって不自然に見えるとセイラム様は真っ青な顔で仰いました。
「……今のような野太い悲鳴もお控え願いたく存じます」
「やだ、ごめんなさい……」
「その言葉遣いもです。肩に力を入れない」
セイラム様はとても手厳しい御方のようです。
私は言われた通りに姿勢を伸ばし、脚を肩幅ほどに開き、両手を軽く握り込むようにして膝に置きました。座っているときは基本的にこの形を崩さなければ良いとのことです。
うぅ、私、これから両親の元へ行くと言うのに……。
──馬車が向かったのは、私の生家であるローレント伯爵邸でした。
つい先日まで過ごしていたはずの我が家が何処か遠く、他人の家のように感じてしまいます。
体の異変が判明するや否や、セイラム様が無理を通して外出を決めてくださったので、伯爵家への訪問通達はまだ届いていないかもしれません。いえ、もしかしたらそれどころではない可能性も──。
「ではリシェル様、先に私がローレント伯爵にお会いしてきます。間違ってもご両親に泣き付いたりしないでくださいね」
「は、はい」
「今のあなたは一国の王子。石の如く鎮座しているだけで構いませんから」
よほど私に対する信用がないのか、セイラム様は馬車から体を離しつつ何度も注意を促しました。そんなに大声を上げていたら屋敷にも聞こえてしまいそうです。大丈夫ですから早く行ってください、と窓から手を振れば、ようやく背を向けてくださいました。
ホッと息をついたのも束の間、誰もいなくなってしまった狭い空間に、私はすぐ心細くなりました。
馭者の方に話しかけられたらどうしましょう。セイラム様がいらっしゃらないと、きっとボロが出てしまいます。あぁ、どうし──。
「いやァァァァ!! リシェル、早く戻って来てちょうだい、お願いよぉ……!!」
悲痛な叫びが外から聞こえ、驚いた私は馬車の扉を蹴破ってしまいました。拉げた扉が草むらの向こうへ消える様を、私は唖然と見送りました。
この体はどうなっているのでしょう。手足が当たっただけで物が壊れてしまうのです、決して私のせいでは……いえ、今は言い訳をしている場合ではありません。
唐突に馬車が大破し青褪める馭者の方には目もくれず、私は急いで外へ飛び出しました。
──え?
か、軽い!
体が軽すぎる!
私、こんなに速く走れたのは人生で初めてです!
凄いですわ、ヴァルト様のお体はこんなにも大きいのに、どうしてこれほど俊敏に動けますの!?
「うおぉ!? ちょ、どちらへ行かれるんですかヴァルト様──」
どうしましょう!
走るのに夢中で、ついセイラム様を追い越してしまいました!
ですが止まれません、止まりたくないのです!
「この脚が動かなくなるまで!!」
「あんたは闘牛か!! 早急に止まれ!!」
「と、闘牛!? 酷いですわセイラム様……!」
セイラム様の発言に崩れ落ちた私でしたが、おかげでようやく我に返りました。ヴァルト様のお体が羽のように軽いからと、人目も憚らず爆走してしまうなんて。きっとこの体には恐ろしい興奮作用があるに違いありません。
おいおいと蹲る私に追いついたセイラム様は、肩で息をしながら険しいお顔でその場に屈みました。
「何ですか、あなたは鳥頭ですか? 先に私が伯爵にお会いしてくると言いましたよね……?」
「あぁぁ、ごめんなさいセイラム様。ですが母の悲鳴が聞こえて、思わず走り出してしまいました」
「悲鳴?」
「えっ、お聞きになりませんでしたか?」
まさか私の聞き違いだったのでしょうか。恥ずかしくて穴に入りたい気分です。この腕なら余裕で硬い地面も掘れてしまいそうですが。
コツコツと石畳を叩き始めた巨漢に危機感を覚えたのか、セイラム様は慌てて私を立ち上がらせました。
「ヴァルト様は耳も良いですから、聞き違いではないと思います」
「まあ……ヴァルト様は人間ではありませんの?」
「その姿じゃなければ不敬罪で処しているところですよ」
やっぱりセイラム様は怖い御方です。いえ、今のは明らかに私の失言でしたけれど。
それにしても、ヴァルト様に対してもこのような態度なのでしょうか。王太子となられる御方に向かってゴリラや闘牛だなんて、普通に考えればそれこそ不敬罪です。
もしかしたら古くからのご友人で、気の置けない仲なのかもしれません。殿方同士の友人関係がどのようなものなのかは存じ上げませんが、きっと砕けた間柄なのでしょう。
「──セイラムじゃないか。こんなところで何をしている」
そのとき、私とセイラム様の元へ小柄な女性が現れました。
長く嫋やかな銀髪を前髪ごと無造作に後ろで束ね、肩まで捲り上げたブラウスからは白い腕が剥き出しになっていました。
何てはしたない格好なのでしょう。ついつい眉を顰めましたが、次の瞬間に私は雄叫びを上げて少女を屋敷の中へ運び込んだのでした。