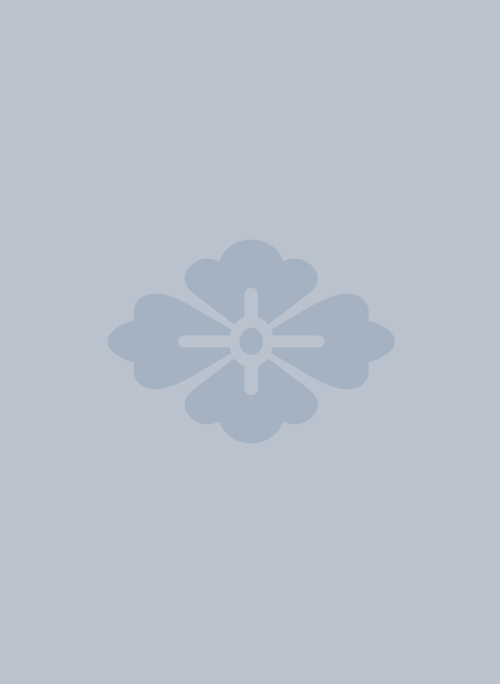嫌いだ。
みんな、大嫌いだ。
療養の為などと言われたが、そんなの嘘に決まっている。
きっと、ここに捨てられたに違いない。
そうじゃないなら、何故こんな所に連れてきた?
敵国との境目にある、小さな町。
側にいてくれるのはやる気のない護衛と、お目付け役のデレクだけ。
みんな、兄がいればいいのだ。
聡明で、いや、何もかも自分より秀でた兄がいれば、それで足りているのだ。
(……でも、私が先に生まれていれば)
何度、そう思ったか。
それでも、どうにかなる問題ではない。
学問や武術、兵法。
お利口な返事。
そのどれを学んでも、出来のいい結果だったとしても、何も変わらない。
――諦めずして、どうればいい?
『アルバート様、絶対にお一人で出歩かないで下さいよ! ここはあの、禁断の森の近くですから』
デレクのお説教は慣れている。
それに実を言うと、この大声が嫌いじゃなかった。
本気で心配してくれる――たとえ、役目だからだとしても――そう実感できるから。
だから、出掛けた。
怒ってほしくて。
心配してほしくて。
大体、デレクは分かっていない。
“禁断”などと言われてしまえば、王子とはいえ、少年が大人しくしていられる訳がないではないか。
どこをどう歩いたのか、まるで覚えてはいない。
六つかそこらの子供の足で、よく無事だったものだ。
いい身なりの子供が、一人ぽつんと立っていたら。
幼少のアルバートとて、考えなかったのではない。
(……いいんだ、どうなったって)
考えたから、歩いているのだ。
誰か――聞きつけた父が、飛んで来てくれるのではないか。
そんな、脆い期待を抱いて。