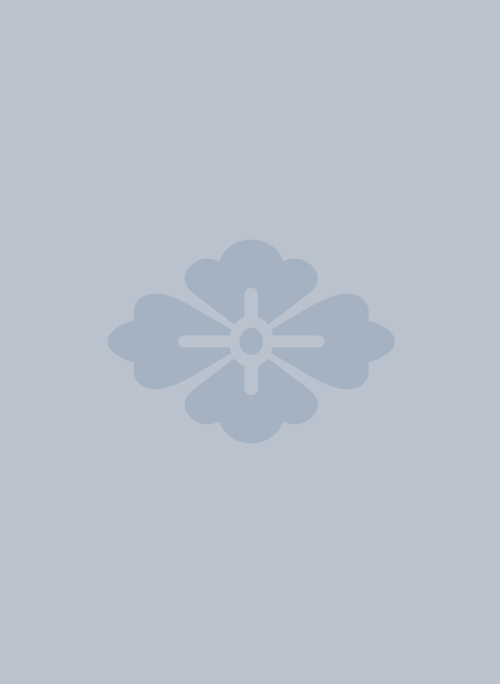ロンドンの冬の夜は長い。
早ければ午後3時には日没を迎えるこの季節。
とうに日没を迎えたという午後5時に、わたしとサラは薄いシルクのワンピース1枚にストールという出で立ちで寒風吹きすさぶロンドンの街中に立っていた。
「ねぇ、サラ。なんでこんな薄着でこんなとこにいなきゃいけないわけ!?」
昼間に学校の近くで胸を握られたわたしは、その時初めてサラの思惑を知り断固拒否をしたのだけど、強引に押し切る友人に手も足も出ず、見事こんな格好をさせられていた。
ワインレッドの大きく胸のあいたワンピースに黒のストール。
わたしは寒いのと恥ずかしいのとで、ストールを大きく広げて胸もとを隠す。
サラは黒のワンピースに白の蝶をあしらった大人っぽい風貌で、かなり目立ちながらわたしの横に立っていた。
「カレン、パーティーホールに入ったらストール没収ね。素敵だもの。すぐに男たちが寄ってくるわよ」
サラは片足を少し前に出したモデル立ちで腕を組みながら自信たっぷりに微笑む。
「それと、会場に入る時は全員仮面をつけるのが決まりだから。これ持っておいて」
サラが差し出したのは、目の回りだけを隠すようになっている鳥の羽のような形をした金色の皮製のマスクだった。
サラも同じものを持ちながら微笑む。
サラの望みは要するに、日本に帰る前にイギリスの男性の素晴らしさを知ってほしいということだった。
今夜限りでも、素敵な恋をしてほしいと。
それには、この「仮面舞踏会」はうってつけだった。
早ければ午後3時には日没を迎えるこの季節。
とうに日没を迎えたという午後5時に、わたしとサラは薄いシルクのワンピース1枚にストールという出で立ちで寒風吹きすさぶロンドンの街中に立っていた。
「ねぇ、サラ。なんでこんな薄着でこんなとこにいなきゃいけないわけ!?」
昼間に学校の近くで胸を握られたわたしは、その時初めてサラの思惑を知り断固拒否をしたのだけど、強引に押し切る友人に手も足も出ず、見事こんな格好をさせられていた。
ワインレッドの大きく胸のあいたワンピースに黒のストール。
わたしは寒いのと恥ずかしいのとで、ストールを大きく広げて胸もとを隠す。
サラは黒のワンピースに白の蝶をあしらった大人っぽい風貌で、かなり目立ちながらわたしの横に立っていた。
「カレン、パーティーホールに入ったらストール没収ね。素敵だもの。すぐに男たちが寄ってくるわよ」
サラは片足を少し前に出したモデル立ちで腕を組みながら自信たっぷりに微笑む。
「それと、会場に入る時は全員仮面をつけるのが決まりだから。これ持っておいて」
サラが差し出したのは、目の回りだけを隠すようになっている鳥の羽のような形をした金色の皮製のマスクだった。
サラも同じものを持ちながら微笑む。
サラの望みは要するに、日本に帰る前にイギリスの男性の素晴らしさを知ってほしいということだった。
今夜限りでも、素敵な恋をしてほしいと。
それには、この「仮面舞踏会」はうってつけだった。