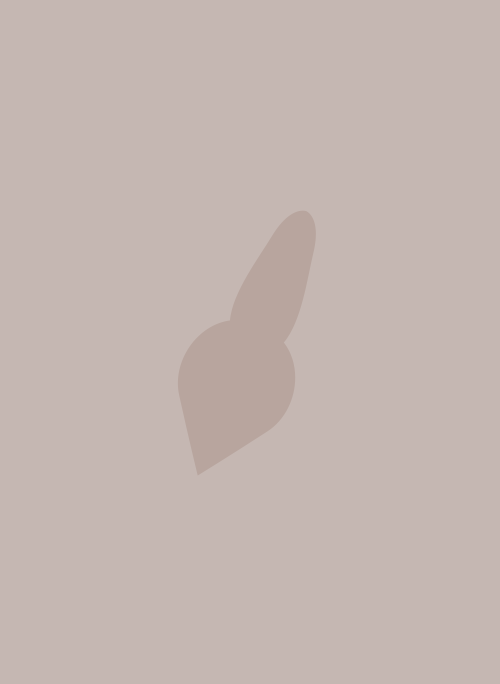三月の、まだ冷たさの残る空気。
校庭の樹の下で集合写真を撮り終え、まとまって校門へ向かう卒業生の私達。
その中で私は、周りと談笑しながら、ずっと彼のことを目で追っている。
彼は私が見ていることには気づいていないようで、いつも通り友達とふざけている。
もう毎日彼を見ることはできないんだと思うと、切なくなり、彼から一旦目を離すものの、結局はまた追ってしまう。
高校の同窓会の招待状が最初に引き出していたのは、その思い出だった。
彼、市川由斗と、学校の敷地内で過ごした最後の数分間。
――久々に会ってみたいな、由斗に。
その思いだけで私は招待状の「出席」の項目にチェックをつけて、ビリビリに破いてしまった封筒の代わりに新しい封筒に入れた。
のりをして切手を貼り、宛名に送り主である主催者の住所を書き、送り主として「白鳥雅弥」と書き込んで、通勤用のバッグに入れた。
*
同窓会の日は、あっという間に来た。
私は、あまり洒落たものではなく、カジュアルな格好をしていこうとTシャツにカーディガンと七分丈のスカートにスニーカーで会場である居酒屋に入った。
この居酒屋は、高校の卒業祝いの懇親会の時にもお世話になった。
当時はまだお酒が飲めなかったのに、なぜ居酒屋を選んだのか。
詳しい経緯は知らないけど、高校から距離が近いから、というのが確か理由の一つにあった。
テキトーといえばテキトーだけど、店を気にしないほど仲がいいとも言えるのが、うちの学年の自慢でもある。
居酒屋ののれんをくぐると、そこにはすでに半数以上の同窓生が集まっていた。
「あ、雅弥!」
私の入店に一番最初に気づいたのは、元学級委員長で、同窓会の主催者である水瀬澪だった。
彼女の一声でみんなも気づき、おおー!と声を上げては手を叩いている人もいる。
それにどう応えればいいのかよくわからず、笑顔で会釈しながら入っていくと、店の奥の一角を見て胃がひっくり返ったような感覚になった。
ほんの少し背が伸び、肩幅が広くなり、暗めの茶色に染められた短髪の、澪の斜め向かいに座ってこちらを見ながら微笑んではいるものの、手は叩いていない男性。
――市川由斗。
中学、高校と夢中になったその笑顔は五年前の面影をしっかり残していた。
「ここおいで!」
澪が自分の隣の席、由斗の向かいの座布団を叩きながら呼んだ。
澪とは普通に仲が良かったこともあるけど、中学三年の時に由斗が好きだとバレたので、気を使ってこの席を確保してくれたのだろう。
極力由斗と目を合わせないよう澪を見ながら席についた。
「なにか飲む?」
「とりあえずレモンサワーお願い。」
「オッケー。」
澪が店員さんを呼んでレモンサワーを頼んでくれると、由斗が話しかけてきた。
「雅弥全然変わらないな。」
どう話しかけようか迷っていたところだったから動揺したけれど、すぐ冷静になれた。
「由斗だってほとんど変わってないじゃん。」
からかうように言ってみると、由斗も笑ってくれた。
そこからは面白いくらいに話が弾んだ。
由斗は国立大学の大学院に入ったらしい。
私は短大を卒業して三年前就職したと伝えたら、「頭良かったし、四年以上のとこ行ってると思った」とびっくりされた。
由斗の横に座っていた鎌谷蓮や、澪もたまに話に入ってきたけど、基本的に二人は二人で別の話をしていた。
やがてお酒が進み、話題は自然と当時の恋バナになった。
「そういや蓮と澪って両想いだったよね?」
隣の二人も同じ話題になったらしかったので、話を振った。
すると二人は否定も肯定もせず、お互いに照れくさそうに微笑み合った。
――何?
二人を交互に見ていると、由斗が説明してくれた。
「知らなかった?二人、今も付き合ってるんだよ。」
聞いて思わずぽかーんとしてしまった。
卒業式の時点では互いに片想いだった二人が今付き合っているとは思わなかった。
「雅弥は誰が好きだったの?」
蓮が居心地悪そうに、でもどこか嬉しそうに訊いてきて、私は口籠った。
本人の前で、今も好きな人の前で、「だった」なんて言いにくい。
ましてや好きなんて。
「えっと。。私は。。」
顔が熱い。
私が三杯目のレモンサワーの氷を眺めながら考えていると、隣から澪が口を出した。
「由斗が好きだったんだよねぇ。」
「ちょっと!」
突然の澪の勝手な暴露に焦って彼女の肩を掴むと、由斗が声を弾ませながら反応した。
「まじで?!俺も雅弥のこと好きだった!」
一瞬で頭が真っ白になった。
――『好きだった』。
ってことは私達は両想いだった?
「だった」ってことはもう気はない?
でも、またもう一度振り向いてもらえるかな?
由斗の言葉が染み込んでいくに連れて、色々と疑問と期待が膨らんだ。
次に耳に届いたのは、澪の残念そうな一言。
「もうちょっと早く気付けば付き合えたかもしれないのにねぇ。」
――『早く気づけば』?
なんで。。どういうこと?
嫌な予感がして澪を見つめていると、由斗が気まずそうに口を開いた。
「俺、婚約者がいるんだ。」
今度は目の前が真っ暗になった。
一瞬だけでも期待を持った自分が馬鹿らしく思えた。
私のことなどまるで気にかける風もなく、由斗は続けた。
「加波澤財団ってところの一人娘に惚れられたんだ。結婚を視野に入れて、友達からでいいから仲良くしたいって。まあまあ勉強もできるし経済学部だし、どこかのボンボンと結婚しなきゃいけないほど景気も不安定じゃないってことで、親も承諾したらしい。彼女にアプローチされるうちに、俺も向こうのこと好きになって。それで条件付きで婚約ってことになった。」
「その一つが、大学院を卒業すること、なんだってよ。お前そんなに勉強熱心な方じゃなかったから最初はびっくりしたよ。」
蓮は私が気を落としていることに気づいていないのか、私に条件の一つの説明をしてから冗談めかして由斗に話し掛けた。
「そっか。。」
そう呟いてグラスに残っていた溶けかけている氷を一つ口の中に入れた。
*
十時を回った頃に二次会の話題が上がった。
ここからが本番、という感じで、二次会を辞退する人は今のところ一人もいない。
澪が中心となってカラオケの大人数用の部屋の予約を取っている。
「二次会どうする?」
澪は私が由斗のことでショックを受けていることに気付いているよう。
わざわざ訊いてくれたので、遠慮なく断った。
みんなが居酒屋の前でこだまする中、私は澪に手を振り、他の友達に気づかれないように俯きながら二次会のカラオケ店とは逆方向に歩み始めた。
居酒屋を中心に店が並ぶ商店街は、十五分程歩いてようやく振り返ってもなんの灯りも見えない程小さくなった。
無風の中、月明かりに照らされた無人の裏路地を通りながら、由斗のことを考えた。
中高生の間は由斗のことが好きで、今まで彼のことがを忘れられず、私は未だに彼氏がいた事がない。
青春は全て彼に捧げた。
なのに由斗は、彼女どころか、婚約者がいる。
由斗が婚約者のことを好きになるまでの間、誰に想いを寄せていたのだろう。
私が彼に寄せてきた想いを、彼はいつまでに私に寄せていたのだろう。
思いを巡らせれば巡らせるほどやるせない気持ちが膨れ上がっていく。
これから一人で由斗のことを考える時間が欲しい。
しっかり気持ちに踏ん切りを付けたい。
でも、家に帰ったらそのまま寝てしまいそう。
どこに行こうか迷いながら歩を進めると、ちょうど大通りに出た。
目の前で「カラオケ」の看板が輝いている。
私は、吸い込まれるように一人でカラオケ店に入った。