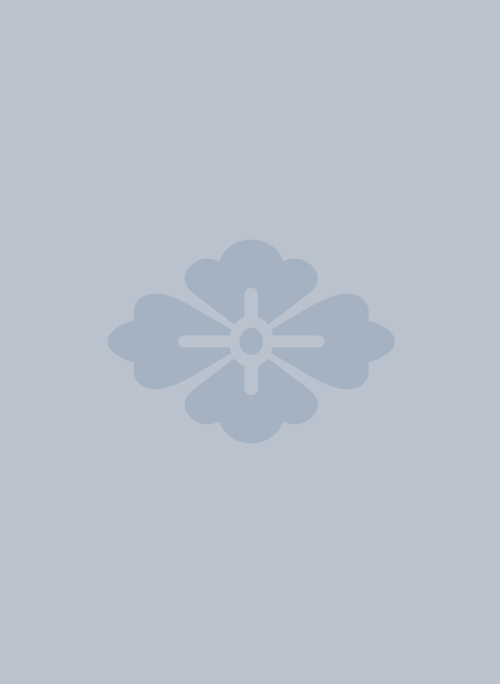「それでは、毛利と大友に国分令(戦などで得た土地を誰に与えるか支持したもの)を出すということで、各々方、宜しいか」
三成の形のよい口から発せられる声は、凛とした響きを持って、左近の耳に伝わった。
諸侯は、それぞれ、応、とか、承知、というような返事を返した。
いまは、九州攻めの軍議(戦いをする前の会議)の最中である。軍議、と言っても、何十人もの大勢でやるのではない。顔ぶれとしては、石田治部(三成)、大谷刑部(吉継)、増田右衛門尉(長盛)、長束大蔵(正家)、黒田官兵衛、豊臣秀吉、秀長、そして、不肖この島左近である。
私は石田三成の一家臣に過ぎないため、本来ならば、このような重要な軍議に参加する資格は無い。が、関白殿下たっての御希望ということで、特別に参加を許されたのである。
「ひとつよろしいか」
官兵衛が、微笑を崩さぬままに声を上げた。
「構いませぬ」
「では。…この二家、とくに毛利などは一枚岩ではない。令を出したとて、上手く通るとは思えませんな」
「では如何なさる」と正家。
「今更変えると言うのは、余り…」と長盛。
「いやなに、毛利と大友に令を出すのは変えずとも構わんさ」
「ではどうするというのだ」
「まあ正家、そういがむでない」
秀吉が、強い尾張訛りで制した。
「しかし、殿下」
「おまえは喧しいのう…おい、官兵衛」
「は、…つまりですな、検使を置くがよろしいかと」
「ははあ…成る程、それなら手っ取り早い」
大谷刑部が初めて口を開いた。
続けざまに、三成が官兵衛に問う。
「では、仮に検使を置くとして、たれが良いと心得られる」
官兵衛は、そうですなあ、とにやにやしながら顎を撫でた。恐らく既に答えは決まっているのだろうが。
「右衛門尉殿は、如何お考えかな」
「わっ、私ですか!? 私などは……いや、まあ、そうですな……毛利には安国寺恵瓊、大友には宮城堅甫などが良いかと思われますが…」
長盛は自信なさげに、しかし具体的且つ的確に名を述べた。
左近も、それがが妥当だろうと、小さく頷いた。
が、官兵衛は、相変わらずにやにやとしたままだ。正直、不気味でさえある。
「黒田殿は、如何お考えなのですか…?」
「ん?いやあ、そうですなあ…」
「いい加減、はっきり申されたらどうなのだ。以前から思うておったが、貴殿のその誤魔化すような物言いは好かん」
正家が、苛立ったように片手で畳を叩いた。
「大蔵殿、お言葉を慎まれよ。軍議の最中であるぞ」
と三成が正家を制す。
「ふん。佐吉、官兵衛殿の肩を持つというのか」
「馬鹿なことを。肩を持つとか持たぬとか…何を言っておるのだ。殿下がお困りであろう」
正家は眉を顰めた。
「豊臣の内々で意見が割れるなど、あってはならぬこと。殿下が良しとするものが黒田殿の策ならば、我等はそれに従えばよい。黒田殿だから従うのではない。それが殿下のお考えだから従うのだ」
三成は、一度たりとも正家の方を見ずに、ひと息でそう言い切った。
甘いな、と、左近は思う。
然様なことは、いちいち指摘されるまでもなく、正家にも分かっていよう。
(分かっておる上で、正家殿はこのようなことを言っているのだ)
何故なら、先程の三成の言葉は、必然的に黒田の権力を高めることになるからだ。
豊富臣下の中で最も経験が高く、計略の才があるのは、黒田官兵衛に他ならない。それゆえ関白が官兵衛を重宝するのは当然のことと言える。
問題は、関白が死んだあとだ。
秀吉という大きな頭を失った豊臣政権を、たれが動かすか。そうなった時、関白が最も信頼を寄せていた者が名乗りを上げるだろう。
即ち、黒田官兵衛である。
今でこそ、石田治部や大谷刑部、武辺で聞こえた加藤主計頭や福島左衛門大夫など、若い衆を気に入って使ってはいるが、それでも、信長の家臣だった頃から仕える官兵衛には適うものではないのだ。
関白には後継者がいない。これは、一見盤石に見える豊臣家の、唯一の弱点だと言えよう。或いは死角だと言ってもいい。
関白の死後、その後継者の座を争って大きな戦が起こるであろうことは想像に難くない。それが起こらぬようにと今回の九州攻めを行うわけであるが、しかし如何せん、万全とは言い難いのである。
我があるじ三成には、秀吉への忠義心はあれど、寧ろその忠義心が、真を見る目を曇らせていると言っても過言ではない。
左近は、老武者のように目を細めた。
「そのようなこと、言われずとも分かっておるわ!儂が言いたいのは…」
いきり立つ正家を尻目に、秀長(秀吉の弟)が、はあ、と溜息をつく。
どうやら、三成と正家の言い合いは、此度だけではない、毎度のことであるようだ。
(なれば、私が止めに入る必要はあるまい)
と判断した左近であったが、結局、正家と三成の言い合いが収まったのは四半刻(約30分後)のことであった。