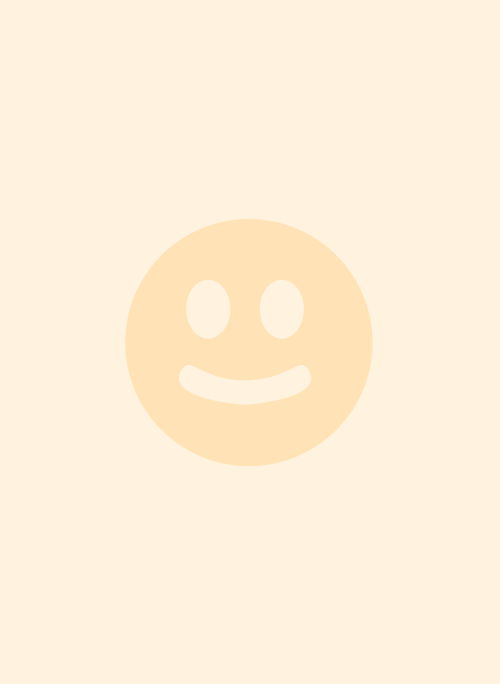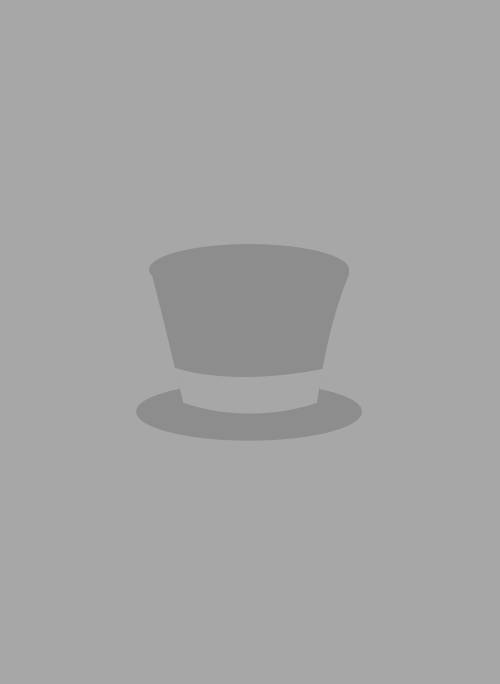ジャンル:青春・友情
テーマ:結婚
制限:「!」や「?」などの記号の使用禁止
登場人物を3人以上登場させる。
作品中に【「それはもう無理かもしれない」】というセリフを必ず入れる。
会話文と地の文の割合を7:3にする。
(字数換算、会話文1400字、地の文600字)
文字数:2000字ぴったり(改行・余白含めて)
というお題で書かせていただいた作品です。
◆ ◆ ◆ ◆
「隠す必要はないとのことなので伝えます。奥さんの余命は三年です」
医師の宣告に俺は言葉を失った。しかし、妻は気丈だった。笑みを浮かべるとこう言ったのだ。
「余命三年、それは他の病院でも同じでしょうか。では、私は三年以上生きますよ。だって、今まで治療に尽くしてくれた勇人先生を名医にしなくてはいけないのですから」
唇を噛んだ医師は妻を見てから俺を見る。そして、無理やりとも思える笑みを浮かべてから口を開いた。
「美代子さんは相変わらずだな。やっぱり、俺じゃあ敵わない」
「勇人だけじゃないよ。僕だってそうさ。美代子にはいつも言い負かされているよ」
「そう聞くと思い出すな。甲子園を目指していたあの頃から、もう五十年も経つのか。俺がキャッチャーで、お前はピッチャー、美代子さんはマネージャー。美代子さんがつくる氷嚢には、いつも助けられていたっけ」
おしゃべりな勇人が、昔を思い出したのか語りはじめる。
「ちょっと二人とも、今は真面目な話をしているのに、話をそらさないでよ。勇人先生も他の患者さんの診療があるんでしょう」
「田舎で主治医もこの通りのじいさんだからね。診療も終わりの時間が近いし、誰もこないと思うよ」
妻の美代子は話題転換が不服なのか頬を膨らませた。けれど俺は知っている。勇人は美代子の性格を知った上で病気ではない話題にしたのだ。
「進とはよく配球で言い争ったよな。それを強気な美代子さんがとめてくれたっけ」
「強気ではないです。言い争っていたら注意するのは当たり前よ」
「そういう割に、美代子はいつも勇人の味方をしていたんだよな」
「そうそう、それで俺のことが好きなのかと思ってさ。思い切って告白したら振られたんだよ。その時に何となくわかったんだ。彼女は俺のことが好きだから味方をしてきたんじゃない。進に投手の仕事だけを真剣にしてほしいからなんだって」
「ちょっと待て。告白したっていうのは初耳だぞ」
まさか勇人が告白していたとは。ずっと秘密にしていたのか。
「両想いみたいだから告白しろよって言ったのは知っていたからだったのか」
「驚いたか。負けたのが悔しくてな。今まで黙っていたんだよ。けれど、今日は言うと決めたんだ。二人にどうしてもしてほしいことがあるから」
意味がわからず、俺と美代子は顔を見合わせる。
「二人にはさ、結婚式をしてほしいんだ」
余命三年の妻にした勇人の提案に唖然としてしまう。しかし、美代子は笑顔をうかべた。
「それは良案ね。あの頃は貧乏で結婚式なんて挙げられなかったから」
「美代子さんなら賛成してくれると思った。幹事は俺が喜んでやらせてもらうよ。あの頃の仲間を呼ぼう。そして、みんなでキャッチボールをするんだ。これから忙しくなるぞ」
勇人の提案で話が進行していく。美代子は反対すると思ったのだが満更でもなさそうだ。
「この年で結婚式なんて照れ臭いのだが」
「今回は観念するんだな。照れ臭くて、今の今まで式を挙げなかったとは言わせないぞ」
勇人の悪戯っぽい笑みが、昔の勇人に見えた。思い出した。野球部の時もこうだった。勇人が場を盛り上げて、俺がそれに冷静に答えて、美代子がその場を整える。切っても切れない大切なつながりを。
「美代子さんに呼んでほしい人を聞かないと。生徒会長はやめてくれよ。俺、あいつは苦手だから」
「勇人がやることは、破天荒なことばかりだったからな。生徒会長の気持ちはわかる気がしていたよ」
「堅物なんだよ。お前もあいつも。もっと人生楽しもうぜ」
「そうそう、勇人さんの言う通り。そして、選ぶのは私よ。けれど二人の期待は裏切らないつもりだから楽しみにしていて」
何故、妻は余命三年だというのに明るくできるのだろうか。いや、俺はこんな妻が好きだから結婚して、今まで助け合ってきたのだ。
そして、俺は勇人と二人で美代子を最期まで笑って支えようと思った。
五年後、誰もいない病室を見ながら俺は息を吐く。隣には勇人がいた。
「ありがとう、勇人。君が結婚式を挙げようと言ってくれなかったら、美代子は違う最期を迎えていたのかもしれない」
「生まれ変わったら、俺たちはまた親友同士だろうな。切っても切れない縁を感じるからさ」
「ああ、そうだな。そして、また俺は美代子と一緒になろう」
「いや、それはもう無理かもしれないぞ。だって、次は俺が美代子さんと結婚するって決めているんだから」
「いや、お前には負ける気がしないし譲れない。次は俺が先に美代子に告白する」
もう、美代子は俺たちの言い争いに参加しない。けれど、お互い顔を合せて笑う。
「あの頃を思い出して、キャッチボールをしようか」
「お前のキレのある変化球を見せてくれよ。あれを取れるのが俺だけだったというのが自慢なんだから」
近くのグラウンドから白球を打つ音が聞こえていた。
テーマ:結婚
制限:「!」や「?」などの記号の使用禁止
登場人物を3人以上登場させる。
作品中に【「それはもう無理かもしれない」】というセリフを必ず入れる。
会話文と地の文の割合を7:3にする。
(字数換算、会話文1400字、地の文600字)
文字数:2000字ぴったり(改行・余白含めて)
というお題で書かせていただいた作品です。
◆ ◆ ◆ ◆
「隠す必要はないとのことなので伝えます。奥さんの余命は三年です」
医師の宣告に俺は言葉を失った。しかし、妻は気丈だった。笑みを浮かべるとこう言ったのだ。
「余命三年、それは他の病院でも同じでしょうか。では、私は三年以上生きますよ。だって、今まで治療に尽くしてくれた勇人先生を名医にしなくてはいけないのですから」
唇を噛んだ医師は妻を見てから俺を見る。そして、無理やりとも思える笑みを浮かべてから口を開いた。
「美代子さんは相変わらずだな。やっぱり、俺じゃあ敵わない」
「勇人だけじゃないよ。僕だってそうさ。美代子にはいつも言い負かされているよ」
「そう聞くと思い出すな。甲子園を目指していたあの頃から、もう五十年も経つのか。俺がキャッチャーで、お前はピッチャー、美代子さんはマネージャー。美代子さんがつくる氷嚢には、いつも助けられていたっけ」
おしゃべりな勇人が、昔を思い出したのか語りはじめる。
「ちょっと二人とも、今は真面目な話をしているのに、話をそらさないでよ。勇人先生も他の患者さんの診療があるんでしょう」
「田舎で主治医もこの通りのじいさんだからね。診療も終わりの時間が近いし、誰もこないと思うよ」
妻の美代子は話題転換が不服なのか頬を膨らませた。けれど俺は知っている。勇人は美代子の性格を知った上で病気ではない話題にしたのだ。
「進とはよく配球で言い争ったよな。それを強気な美代子さんがとめてくれたっけ」
「強気ではないです。言い争っていたら注意するのは当たり前よ」
「そういう割に、美代子はいつも勇人の味方をしていたんだよな」
「そうそう、それで俺のことが好きなのかと思ってさ。思い切って告白したら振られたんだよ。その時に何となくわかったんだ。彼女は俺のことが好きだから味方をしてきたんじゃない。進に投手の仕事だけを真剣にしてほしいからなんだって」
「ちょっと待て。告白したっていうのは初耳だぞ」
まさか勇人が告白していたとは。ずっと秘密にしていたのか。
「両想いみたいだから告白しろよって言ったのは知っていたからだったのか」
「驚いたか。負けたのが悔しくてな。今まで黙っていたんだよ。けれど、今日は言うと決めたんだ。二人にどうしてもしてほしいことがあるから」
意味がわからず、俺と美代子は顔を見合わせる。
「二人にはさ、結婚式をしてほしいんだ」
余命三年の妻にした勇人の提案に唖然としてしまう。しかし、美代子は笑顔をうかべた。
「それは良案ね。あの頃は貧乏で結婚式なんて挙げられなかったから」
「美代子さんなら賛成してくれると思った。幹事は俺が喜んでやらせてもらうよ。あの頃の仲間を呼ぼう。そして、みんなでキャッチボールをするんだ。これから忙しくなるぞ」
勇人の提案で話が進行していく。美代子は反対すると思ったのだが満更でもなさそうだ。
「この年で結婚式なんて照れ臭いのだが」
「今回は観念するんだな。照れ臭くて、今の今まで式を挙げなかったとは言わせないぞ」
勇人の悪戯っぽい笑みが、昔の勇人に見えた。思い出した。野球部の時もこうだった。勇人が場を盛り上げて、俺がそれに冷静に答えて、美代子がその場を整える。切っても切れない大切なつながりを。
「美代子さんに呼んでほしい人を聞かないと。生徒会長はやめてくれよ。俺、あいつは苦手だから」
「勇人がやることは、破天荒なことばかりだったからな。生徒会長の気持ちはわかる気がしていたよ」
「堅物なんだよ。お前もあいつも。もっと人生楽しもうぜ」
「そうそう、勇人さんの言う通り。そして、選ぶのは私よ。けれど二人の期待は裏切らないつもりだから楽しみにしていて」
何故、妻は余命三年だというのに明るくできるのだろうか。いや、俺はこんな妻が好きだから結婚して、今まで助け合ってきたのだ。
そして、俺は勇人と二人で美代子を最期まで笑って支えようと思った。
五年後、誰もいない病室を見ながら俺は息を吐く。隣には勇人がいた。
「ありがとう、勇人。君が結婚式を挙げようと言ってくれなかったら、美代子は違う最期を迎えていたのかもしれない」
「生まれ変わったら、俺たちはまた親友同士だろうな。切っても切れない縁を感じるからさ」
「ああ、そうだな。そして、また俺は美代子と一緒になろう」
「いや、それはもう無理かもしれないぞ。だって、次は俺が美代子さんと結婚するって決めているんだから」
「いや、お前には負ける気がしないし譲れない。次は俺が先に美代子に告白する」
もう、美代子は俺たちの言い争いに参加しない。けれど、お互い顔を合せて笑う。
「あの頃を思い出して、キャッチボールをしようか」
「お前のキレのある変化球を見せてくれよ。あれを取れるのが俺だけだったというのが自慢なんだから」
近くのグラウンドから白球を打つ音が聞こえていた。