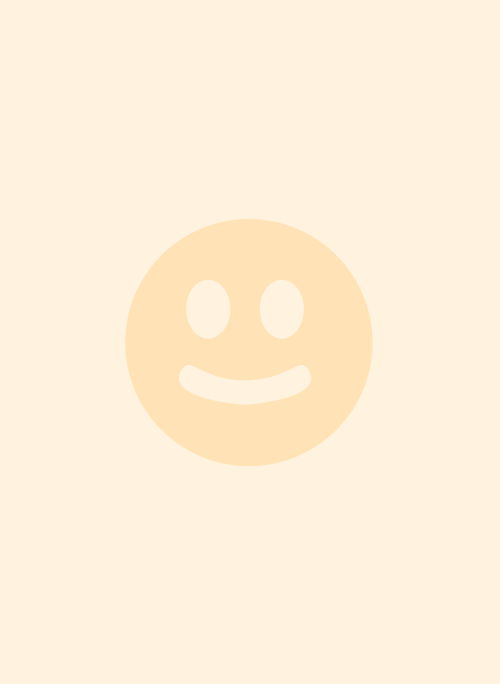自転車に乗れるようになったのはいつだっただろうか。
あんな不安定なものに乗れるなんて自分でも信じられない。
どうやって乗れるようになったのか? どこで乗れるようになったのか? 誰に乗れるように教えてもらったのか?
まるで覚えていない。
だけど私は乗れるのだ。
サドルの手前をまたぎ右足で高くなったほうのペダルを踏み込みながら上半身を浮かせ、半回転したもう片方のペダルに左足を乗せてサドルに腰を下ろす。するとどうだろう。気が付けば私の足はいつもの地面から離れ、私の体は走るより速く前に進み、私の髪はドライヤーと比べ物にならないほど風に乗って棚引くのだ。
何年か振りに乗った自転車は私の意志をハンドルから正確に読み取り、右へ左へ行きたい方向へ導いてくれる。
中学生の頃、毎日のように使ったいくつかの道は私を温かく迎えてくれて、古びた豆腐屋の看板も均一に並ぶ街路樹もぶつかったことのある電信柱も皆、私に優しかった。雨が降るといつも水溜りになっていた道路は綺麗に舗装されていて少し寂しい思いもしたが、文房具屋の角にある緑色をした猫の人形はそのままだったので安心した。洗面器くらいの台座の上でスキップをしている緑色の猫はいつも右手に黒く光る万年筆を掲げていて、それが彼にとってとても大切なものであることを象徴していた。毎日学校の行き帰りでそれを眺めては、いつしか私も万年筆を手に入れて私にしかない素敵な物語を刻みたいと夢見ていた。
実際、高校一年生の冬休みから私は近くの弁当屋でアルバイトをし始め、最初にもらったお給料で両親にケーキ(母にレアチーズケーキ、父にガトーショコラ)をプレゼントし、自分へのご褒美として万年筆を買った(そこに苺のショートケーキも含まれていたが)。しかし、一万円もした万年筆は上手に扱うことが出来ず、すぐにインクを垂らしてしまったり紙に引っ掛けてしまったりした。素敵な物語も全く浮かばなかった。一ヶ月もしないうちに勉強机の奥にしまい込まれた緑色の猫が持つものに負けないくらい黒く輝き、魅力的で神秘に溢れた私の宝物は一体どこに消えてしまったのだろう。
就職が決まり一人暮らしをする時に勉強机と共に捨てられてしまったのだろうか。それともまだ私に物語を刻ませようと、どこかでひっそりと待っているのだろうか。
あんな不安定なものに乗れるなんて自分でも信じられない。
どうやって乗れるようになったのか? どこで乗れるようになったのか? 誰に乗れるように教えてもらったのか?
まるで覚えていない。
だけど私は乗れるのだ。
サドルの手前をまたぎ右足で高くなったほうのペダルを踏み込みながら上半身を浮かせ、半回転したもう片方のペダルに左足を乗せてサドルに腰を下ろす。するとどうだろう。気が付けば私の足はいつもの地面から離れ、私の体は走るより速く前に進み、私の髪はドライヤーと比べ物にならないほど風に乗って棚引くのだ。
何年か振りに乗った自転車は私の意志をハンドルから正確に読み取り、右へ左へ行きたい方向へ導いてくれる。
中学生の頃、毎日のように使ったいくつかの道は私を温かく迎えてくれて、古びた豆腐屋の看板も均一に並ぶ街路樹もぶつかったことのある電信柱も皆、私に優しかった。雨が降るといつも水溜りになっていた道路は綺麗に舗装されていて少し寂しい思いもしたが、文房具屋の角にある緑色をした猫の人形はそのままだったので安心した。洗面器くらいの台座の上でスキップをしている緑色の猫はいつも右手に黒く光る万年筆を掲げていて、それが彼にとってとても大切なものであることを象徴していた。毎日学校の行き帰りでそれを眺めては、いつしか私も万年筆を手に入れて私にしかない素敵な物語を刻みたいと夢見ていた。
実際、高校一年生の冬休みから私は近くの弁当屋でアルバイトをし始め、最初にもらったお給料で両親にケーキ(母にレアチーズケーキ、父にガトーショコラ)をプレゼントし、自分へのご褒美として万年筆を買った(そこに苺のショートケーキも含まれていたが)。しかし、一万円もした万年筆は上手に扱うことが出来ず、すぐにインクを垂らしてしまったり紙に引っ掛けてしまったりした。素敵な物語も全く浮かばなかった。一ヶ月もしないうちに勉強机の奥にしまい込まれた緑色の猫が持つものに負けないくらい黒く輝き、魅力的で神秘に溢れた私の宝物は一体どこに消えてしまったのだろう。
就職が決まり一人暮らしをする時に勉強机と共に捨てられてしまったのだろうか。それともまだ私に物語を刻ませようと、どこかでひっそりと待っているのだろうか。