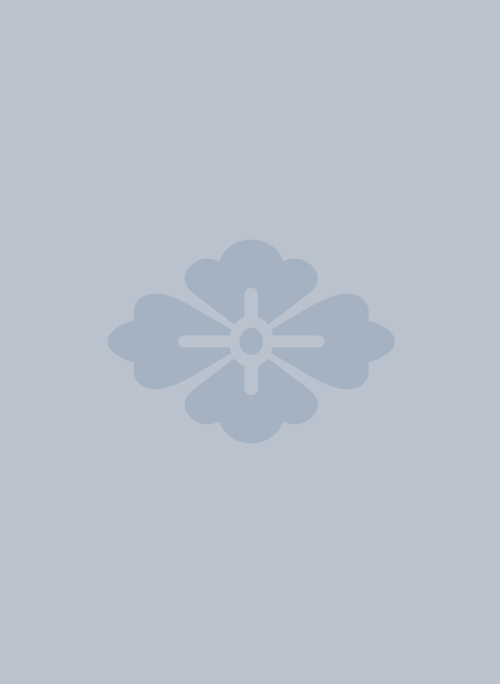「まぁ、一応頭を下げたし、マルクにも頭を下げられちゃあな……」
「ああ。だな……」
互いに顔を見合わせてそう言う男達に、マルクはほっとした表情で言った。
「ありがとうございます、皆さん」
「やめてくれ、兄貴!」
だが、それをぶち壊したのは、ジョルジュのその叫びだった。
「俺は、兄貴の荷物なんかになりたかないんだよ!」
「何も、そういう意味で言ったのでは……」
「自分の落とし前は、自分でつける!」
「では、一人で戦場に出てみますか? それとも、私と組んでみます?」
ニコリと微笑みシモーヌに、ジョルジュは目を丸くした。
「お前……本気かよ? 俺は、昨日、あんなことをしたんだぜ?」
「ええ、そうですね。我を失ってらっしゃったようでした。でも、バートさんも別に気にとめてらっしゃらないようですから、私もあれはあれで、済んだことだと水に流そうと思っているのですが、いけませんか?」
シモーヌのその言葉にジョルジュは首を何度も横に振った。少し赤い顔で。
「い、いや! お、俺もそれでいい! その……お前さえ良ければ、だけどな……」
ジョルジュがそう言いながら、自分より少し背の高い少女を上目遣いに見ると、彼女は微笑んだ。
「私も構いませんよ。ジョルジュさんともう少しお話をしたいと思っていましたので。ただ、昨日の今日では、流石にジャンも治ってませんから、騎馬以外でお相手することになると思いますが、いいですか?」
「ジャンって、あの馬か?」
「はい」
「そんなに悪いのか?」
少し遠慮がちにジョルジュが尋ねると、シモーヌは首を横に振った。
「傷口も化膿していませんので、数週間で復帰出来ると思います」
「良かった!」
「ジョルジュ!」
間髪入れずに、マルクが怖い表情で名を呼ぶと、彼はムッとした表情になった。
「良かった、じゃないでしょう? ちゃんと謝らなければ!」
「だけどよ、兄貴、戦場でのことは恨みっこなしだって言ったのは、兄貴だぜ?」
「それはそうですが、一旦仕事が終われば、仲間でしょう。迷惑をかけたと思ったのなら、謝るべきでしょう」
「チェッ!」
舌打ちすると、ジョルジュはシモーヌの方を向いた。少し赤い顔でプイと横を向いているものの、一応謝ろうとは思っているようだった。すねた子供のようだったが。
「もういいですよ、ジョルジュさん。私も大事なジャンをあんな所に連れて行ったのが悪いと思って、反省したんですから……」
「そんなにあの馬、大事なのか?」
「ええ。大好きな方がくれたものですから」
「大好きな方……?」
そう繰り返すジョルジュの声は小さく、明らかに落胆しているのが見てとれた。
「高そうな馬だったもんな……」
「ええ。わざわざイギリスの名馬の子を送ってくれたと聞いてます」
「イギリスの?」
ジョルジュは目を丸くした。
現在、イギリスとフランスは戦闘状態とはいえど、フランドル地方などは、未だにイギリスとの貿易で利益を得ているし、他の地方でもそれで生計を立てている商人もいる。だから、イギリスの馬だと聞いても、不思議は無かったのだが、それでも「名馬」と聞くと、彼女がイギリスの名門の娘ではないのかとの思いが頭をよぎったのだった。
でも、名前が「シモーヌ」ってことは、母親はこっち(=フランス)の人間ってことだよな?
そんなことを思いながら、彼がチラリと彼女を見ると、彼女は微笑んだ。
「ああ。だな……」
互いに顔を見合わせてそう言う男達に、マルクはほっとした表情で言った。
「ありがとうございます、皆さん」
「やめてくれ、兄貴!」
だが、それをぶち壊したのは、ジョルジュのその叫びだった。
「俺は、兄貴の荷物なんかになりたかないんだよ!」
「何も、そういう意味で言ったのでは……」
「自分の落とし前は、自分でつける!」
「では、一人で戦場に出てみますか? それとも、私と組んでみます?」
ニコリと微笑みシモーヌに、ジョルジュは目を丸くした。
「お前……本気かよ? 俺は、昨日、あんなことをしたんだぜ?」
「ええ、そうですね。我を失ってらっしゃったようでした。でも、バートさんも別に気にとめてらっしゃらないようですから、私もあれはあれで、済んだことだと水に流そうと思っているのですが、いけませんか?」
シモーヌのその言葉にジョルジュは首を何度も横に振った。少し赤い顔で。
「い、いや! お、俺もそれでいい! その……お前さえ良ければ、だけどな……」
ジョルジュがそう言いながら、自分より少し背の高い少女を上目遣いに見ると、彼女は微笑んだ。
「私も構いませんよ。ジョルジュさんともう少しお話をしたいと思っていましたので。ただ、昨日の今日では、流石にジャンも治ってませんから、騎馬以外でお相手することになると思いますが、いいですか?」
「ジャンって、あの馬か?」
「はい」
「そんなに悪いのか?」
少し遠慮がちにジョルジュが尋ねると、シモーヌは首を横に振った。
「傷口も化膿していませんので、数週間で復帰出来ると思います」
「良かった!」
「ジョルジュ!」
間髪入れずに、マルクが怖い表情で名を呼ぶと、彼はムッとした表情になった。
「良かった、じゃないでしょう? ちゃんと謝らなければ!」
「だけどよ、兄貴、戦場でのことは恨みっこなしだって言ったのは、兄貴だぜ?」
「それはそうですが、一旦仕事が終われば、仲間でしょう。迷惑をかけたと思ったのなら、謝るべきでしょう」
「チェッ!」
舌打ちすると、ジョルジュはシモーヌの方を向いた。少し赤い顔でプイと横を向いているものの、一応謝ろうとは思っているようだった。すねた子供のようだったが。
「もういいですよ、ジョルジュさん。私も大事なジャンをあんな所に連れて行ったのが悪いと思って、反省したんですから……」
「そんなにあの馬、大事なのか?」
「ええ。大好きな方がくれたものですから」
「大好きな方……?」
そう繰り返すジョルジュの声は小さく、明らかに落胆しているのが見てとれた。
「高そうな馬だったもんな……」
「ええ。わざわざイギリスの名馬の子を送ってくれたと聞いてます」
「イギリスの?」
ジョルジュは目を丸くした。
現在、イギリスとフランスは戦闘状態とはいえど、フランドル地方などは、未だにイギリスとの貿易で利益を得ているし、他の地方でもそれで生計を立てている商人もいる。だから、イギリスの馬だと聞いても、不思議は無かったのだが、それでも「名馬」と聞くと、彼女がイギリスの名門の娘ではないのかとの思いが頭をよぎったのだった。
でも、名前が「シモーヌ」ってことは、母親はこっち(=フランス)の人間ってことだよな?
そんなことを思いながら、彼がチラリと彼女を見ると、彼女は微笑んだ。