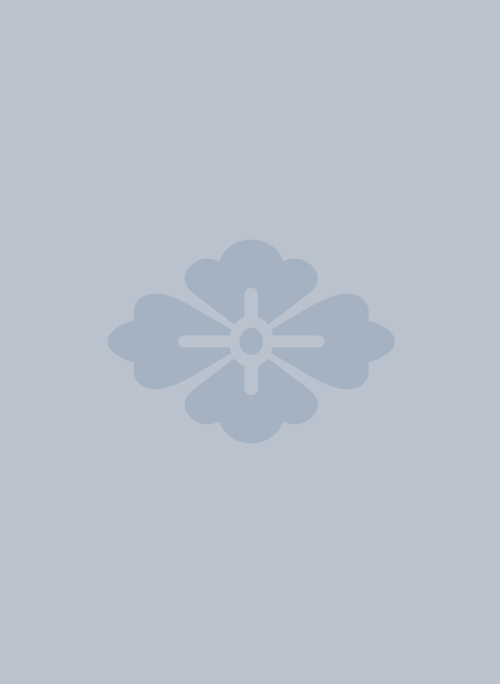こぉん……
こぉん……
狐の鳴き声のような音が響く。
ここは稲荷神社。
賽銭箱の前に銀狐が座っている。
「あー……」
死んだ魚のような目で銀狐は欠伸をする。
「俺がこんなところに居たところで何のご利益もねぇっつーの。ニンゲンって何でああも迷信を真に受けるんだよ。」
そう言うと賽銭箱を覗き込む。
「住職は儲かったりって感じだけど。」
そう呟くとヒトの気配がした。
「住職儲かったり、か。」
ヒトは銀狐を抱き上げる。
そして、銀狐がそうしていたようにヒトも賽銭箱の前に座った。
「何だよ。本当のことだろーが。」
「神社の修理や我々の寝食で使用するのであって、娯楽ではない。」
生真面目にヒトは言う。
「色気ねーな。」
「それは此方の台詞だ。ヌシも女の一人や三人連れてきたらどうだ。」
「女狐連れて何が楽しいんだよ。」
「だったら、ニンゲンや狸でも良いんだぞ?」
「お断りだ。」
銀狐は不快そうだ。
「…………本当にヌシには感謝している。」
ヒトはぽつりと零すように言った。
「一人だったワレに居場所をくれた。」
「こぉん。」
鼻で笑うように銀狐は鳴く。
『かぁさま、かぁさま、どうしておいてくの?』
『貴方は神への供え物なのです。』
村の慣わしで寂れた神社に供えられたヒト。
一人で神へ祈りながら死ぬ定め。
外の世界を知る術は無かった。
顔を隠した黒子のような人物が神子に供えるように衣食を捧げる。
しかし、口をきいてはくれない。
そんなある日に出会った狐。
『ニンゲンって盲目だよな。何かに縋って生きるしか知らねーんだから。』
面白可笑しく話しかける銀狐にヒトは目を丸くした。
何年ぶりに聞く自分への声だろう。
外の喧騒ではない。
間違えなく、自分へのものだ。
『この神社に居てやるよ。』
唐突にそう言って居座った銀狐をヒトは受け入れた。
否定することもこの世の何ひとつ知らないヒトと知り尽くした銀狐。
いつしか、慣わしは廃れていく。
そして、代わりにこの神社を稲荷神社として崇めた。
“銀狐が厄から守ってくれる”
そんな迷信に変わっていった。
「数年でニンゲンは変わるものだな。」
「都合が良かっただけだろう。」
ヒトに銀狐は言う。
「それに、この神社をここまで整備したりしたのは賽銭とお前のおかげだ。俺は此処に居るだけさ。」
「ヌシが居たから、ワレはひとりではない。」
「……ははっ。トモダチつくれよ。」
銀狐は目を細めて言った。
「友達なら居る。」
きっぱりとヒトは言った。
それに驚くように銀狐は目を丸くして見上げた。
「ヌシだ。」
その言葉に呆気に取られて銀狐は瞬きをする。
「ばぁか。そういうことじゃねーよ。」
ぷいっとそっぽを向く。
「違うのか?」
その問いに答えずに銀狐は鳴く。
「こぉん。」
ばか。
俺以外の友達ってことだよ。
こぉん……
狐の鳴き声のような音が響く。
ここは稲荷神社。
賽銭箱の前に銀狐が座っている。
「あー……」
死んだ魚のような目で銀狐は欠伸をする。
「俺がこんなところに居たところで何のご利益もねぇっつーの。ニンゲンって何でああも迷信を真に受けるんだよ。」
そう言うと賽銭箱を覗き込む。
「住職は儲かったりって感じだけど。」
そう呟くとヒトの気配がした。
「住職儲かったり、か。」
ヒトは銀狐を抱き上げる。
そして、銀狐がそうしていたようにヒトも賽銭箱の前に座った。
「何だよ。本当のことだろーが。」
「神社の修理や我々の寝食で使用するのであって、娯楽ではない。」
生真面目にヒトは言う。
「色気ねーな。」
「それは此方の台詞だ。ヌシも女の一人や三人連れてきたらどうだ。」
「女狐連れて何が楽しいんだよ。」
「だったら、ニンゲンや狸でも良いんだぞ?」
「お断りだ。」
銀狐は不快そうだ。
「…………本当にヌシには感謝している。」
ヒトはぽつりと零すように言った。
「一人だったワレに居場所をくれた。」
「こぉん。」
鼻で笑うように銀狐は鳴く。
『かぁさま、かぁさま、どうしておいてくの?』
『貴方は神への供え物なのです。』
村の慣わしで寂れた神社に供えられたヒト。
一人で神へ祈りながら死ぬ定め。
外の世界を知る術は無かった。
顔を隠した黒子のような人物が神子に供えるように衣食を捧げる。
しかし、口をきいてはくれない。
そんなある日に出会った狐。
『ニンゲンって盲目だよな。何かに縋って生きるしか知らねーんだから。』
面白可笑しく話しかける銀狐にヒトは目を丸くした。
何年ぶりに聞く自分への声だろう。
外の喧騒ではない。
間違えなく、自分へのものだ。
『この神社に居てやるよ。』
唐突にそう言って居座った銀狐をヒトは受け入れた。
否定することもこの世の何ひとつ知らないヒトと知り尽くした銀狐。
いつしか、慣わしは廃れていく。
そして、代わりにこの神社を稲荷神社として崇めた。
“銀狐が厄から守ってくれる”
そんな迷信に変わっていった。
「数年でニンゲンは変わるものだな。」
「都合が良かっただけだろう。」
ヒトに銀狐は言う。
「それに、この神社をここまで整備したりしたのは賽銭とお前のおかげだ。俺は此処に居るだけさ。」
「ヌシが居たから、ワレはひとりではない。」
「……ははっ。トモダチつくれよ。」
銀狐は目を細めて言った。
「友達なら居る。」
きっぱりとヒトは言った。
それに驚くように銀狐は目を丸くして見上げた。
「ヌシだ。」
その言葉に呆気に取られて銀狐は瞬きをする。
「ばぁか。そういうことじゃねーよ。」
ぷいっとそっぽを向く。
「違うのか?」
その問いに答えずに銀狐は鳴く。
「こぉん。」
ばか。
俺以外の友達ってことだよ。