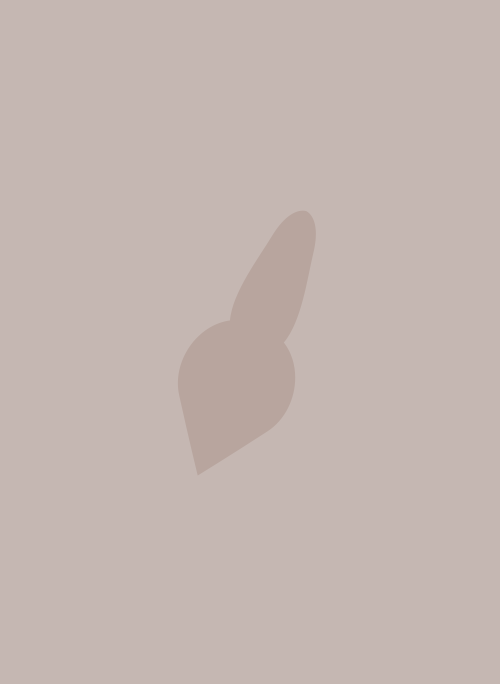国道に入った魔鈴と美里はその速度を落とさずに走り続ける。巡航速度で走る車を右へ左へと追い越していく。
やがて前方に古い型の中古車が見えてくる。 それを見た魔鈴は更に速度を上げる。
美里の本能がそれこそ追っていた車だと告げてくる。
美里はエンジンに再びトルクを与える。
エンジンが悲鳴を上げて後輪で激しく路面を蹴る。
背後から複数のサイレンの音が近づいてくる。
後方の異変に気づき、加瀬は美鈴を撫ででいた左手をギヤに戻し、再び車の制御に神経を集中した。加瀬の本能が自らの危険を告げてくる。
加瀬は思い切りアクセルを踏み込む。
だが、彼の指示を緩慢に受け止めたのか、車はなかなか速度を上げようとはしない。
苛立ちを感じた加瀬は更にアクセルを踏み込む。
その時、加瀬の車の横を一台の赤いバイクが矢のように走り抜けていく。
加瀬の車の前に回り込んだ美里は、急ブレーキをかけた。思いもかけない命令にバイクの後輪は悲鳴をあげて滑り始める。
美里は暴れ馬のようになったバイクをtきから任せに抑え込み,車体を傾けていく。
バイクは横滑りをしながら急速に速度を落としていく。
「うわぁ」
急に目の前に現れた障害物に驚き、加瀬はブレーキを床まで踏み込んだ。今度は加瀬の命令を忠実に受け止めて、車は急速に停まり始めた。
四輪のタイヤは悲鳴をあげ、ハンドルが暴れ出す。
加瀬は左右に振れるハンドルを抑えつけるのが精一杯だった。しかし、ハンドルは抑えつける力から逃れ、大きく左に切れた。
車は緩やかに回転を始めた。
世界が回り始めることを感じた美鈴は声の限りに悲鳴をあげた。
やがて一台のバイクと一台の車は、数メートルの間隔を開けて完全に停止した。
その周囲を取り囲むようにやっと追いついた複数のパトカーが停車した。
やがて前方に古い型の中古車が見えてくる。 それを見た魔鈴は更に速度を上げる。
美里の本能がそれこそ追っていた車だと告げてくる。
美里はエンジンに再びトルクを与える。
エンジンが悲鳴を上げて後輪で激しく路面を蹴る。
背後から複数のサイレンの音が近づいてくる。
後方の異変に気づき、加瀬は美鈴を撫ででいた左手をギヤに戻し、再び車の制御に神経を集中した。加瀬の本能が自らの危険を告げてくる。
加瀬は思い切りアクセルを踏み込む。
だが、彼の指示を緩慢に受け止めたのか、車はなかなか速度を上げようとはしない。
苛立ちを感じた加瀬は更にアクセルを踏み込む。
その時、加瀬の車の横を一台の赤いバイクが矢のように走り抜けていく。
加瀬の車の前に回り込んだ美里は、急ブレーキをかけた。思いもかけない命令にバイクの後輪は悲鳴をあげて滑り始める。
美里は暴れ馬のようになったバイクをtきから任せに抑え込み,車体を傾けていく。
バイクは横滑りをしながら急速に速度を落としていく。
「うわぁ」
急に目の前に現れた障害物に驚き、加瀬はブレーキを床まで踏み込んだ。今度は加瀬の命令を忠実に受け止めて、車は急速に停まり始めた。
四輪のタイヤは悲鳴をあげ、ハンドルが暴れ出す。
加瀬は左右に振れるハンドルを抑えつけるのが精一杯だった。しかし、ハンドルは抑えつける力から逃れ、大きく左に切れた。
車は緩やかに回転を始めた。
世界が回り始めることを感じた美鈴は声の限りに悲鳴をあげた。
やがて一台のバイクと一台の車は、数メートルの間隔を開けて完全に停止した。
その周囲を取り囲むようにやっと追いついた複数のパトカーが停車した。