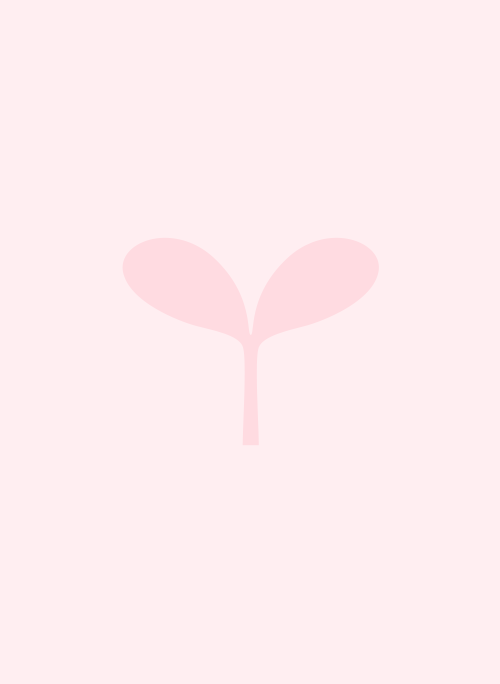それ以降、毎日紗綾に逢う事ができた。夢の中の世界の景色は少しぼやけているけれど、起きてからも夢の内容ははっきり覚えているようになったのだ。
五線譜付きのルーズリーフにわざわざメモをとる必要がなくなり、2Bの鉛筆は二本ともペンケースの中に入っている。
そしてここ数日間の夢には変化が現れてきた。それは、
――ブラックホール。
地球上にブラックホールなんてある訳がない。そんな事はわかっている。けれど、どう見てもあれはブラックホールである。
紗綾はブラックホールの事を知っているのだろうか。僕は今日の夜訊いてみる事にした。
六月も半ばを迎えている。梅雨時特有の風を一切伴う事のない、地面に対して直角に落ちてくる雨に打たれながら、僕は大学近くのバス停へ向かっていった。
ビニール傘は持ってきたのだけれど、朝電車に置き忘れてしまったのだ。
「あっ、ヒロ!」
聞き覚えのある柔らかな女性の声が僕を引き止めた。
「ん? 京香?」
「はい、そうです。『しゃべらなければいい女』の京香です」
諒太の野郎、チクりやがったな。
「あ、いや。それは、その……」
僕はしどろもどろしながら頭を掻いた。
「その言葉の後半は当たってるから許してあげるよ。そんな事よりあんたびしょびしょじゃん。傘入んなよ」
「悪いな。朝電車に傘忘れちゃってさ」
京香はバッグからハンカチを取り出し僕の頭や肩を拭き始めた。
「もう! 中学生じゃないんだから」
「すみません」
たじたじになった僕を見て可笑しかったのだろう。京香はプッと吹き出した。
僕は京香の傘に入れてもらいバス停までゆっくり歩いた。
「あのさあ、京香」
「何?」
「お前、絶対170cm以上あるだろ」
「はあ? 169cmだし!」
「怒んないから本当の事言ってみ」
「はあ? 本当だし! 私が嘘ついてるとでも思ってるの?」
「思ってるって思ってるの?」
「思ってるんでしょ?」
「思ってる」
「もう! 嫌い!」
京香は僕から離れ、僕は再び雨に打たれた。
バスは比較的すいていた。僕たちは中央より少し後方の二人席に並んで座った。次第に乗客が増えてくる。
――次は市民病院前。お降りの方は柱のボタンを押してお知らせ下さい。
録音されたいつもの感情を持たないメッセージが流れる。僕は小さな頃から疑問に思っていた。このバスのアナウンス、バス会社の女性社員の方の声なのだろうか。それとも地元テレビ局のアナウンサーの方などに依頼したものなのだろうか。
そんなどうでもいい事を考えていると市民病院前のバス停で診察を終えたであろう老人が沢山入ってきた。
僕はすっと立ち上がり目の前の腰を曲げた老婆に「どうぞ」と告げた。
「すみませんね。ありがとうございます」
しゃがれた声でお礼を言った老婆は「よっこいしょ」と口ずさみ京香の隣に座る。そして京香と僕の顔を順番に見た。
「あら、ごめんなさいね。恋人同士のお邪魔をしてしまったようね」
「違います!」「違うんです!」
老婆は息の合った僕たちの否定文ににこりと笑う。
「まあまあ、お若いんですからそんなに早く結論をお出しにならない方がいいですよ」
老婆はそう言って次のバス停で降りていった。
――なんだよ。一駅かよ。
僕は再び京香の隣に座った。
「おせっかいな婆ちゃんだったな」
「う、うん。だね」
なんだか京香の様子がおかしい。落ち込んでいるような、元気のないような……。
「どした?」
僕は彼女の顔を覗き込む。
「別に」
京香はそう言って俯いた。
「あのさあ、京香」
「何よ」
「彼女いない歴が二十一年近い僕が言っても説得力ないと思うけどさ」
「だから何?」
「元気のない女の子に『どうしたの?』って訊いて、『別に』って答えた人でね、本当に『別に』だった事っていないんだよ」
「だから?」
「僕たち親友だろ? だから何でも話してよ」
「親友? そうだよね。私たちはただの親友なんだよね」
――ピンポーン。
終点の駅まではまだ二つもバス停がある。けれど京香は柱のボタンを押した。
「買い物して帰るから。じゃあね」
京香が降りた場所はへんぴな住宅街だった。買い物のできる場所などない。
「京香……」
駅に着いた僕はバッグから定期を取り出す。僕の前には小学生らしき少女が定期を自動改札口にかざした。
――ピヨピヨ。
小人料金が適用される電子音が僕の目の前で音をたてた。
鉄道会社は何を根拠に小学生だと判断しているのだろう。身長? しかし170cmを越える小学生は希ではない。
僕が開札を通ると「ピッ」といつもの大人用の音がした。
さすがに185cmの小学生はいないのだろう。
僕はいつもの電車に乗りいつもの駅で降りた。雨は相変わらず降っている。ここから徒歩で十分、雨の中を歩くと思うと気が重くなる。
「あら、岡君? お帰りなさい」
またもや聞き覚えのある声がする。振り返るとそこには寮母さんの優しい笑顔があった。
「あ、寮母さん。どうしたんですか? そんなにいっぱい荷物持って。僕持ちますよ」
「わあ、岡君。助かるわ。今日は夕食を食べる人が十人しかいなくてね。奮発してメロン買ったのよ。今日いない人には内緒よ」
「メロンですか! やった! 絶対他言しません。みんなにも僕から言っておきます」
雨の中を十分も歩くのかと憂鬱になっていたけれど、寮母さんはタクシーに向かって皺いっぱいの右手を上げた。そして僕も便乗させてもらう事になる。
僕は夕食のデザートに甘いメロンを食べた。口に入れた途端とろけるように消えてなくなっていく。
「うんめっ!」
そこに居合わせた十人は口をつぐむ事を約束した。
夕食後、僕は宿題である作曲の続きをした。音符を書いては消し、そしてまた書く。結局今日書いたのはわずかに一行だった。
ふと窓の外に目をやると冷たそうな雨が音もなく降り続けていた。防音施設なので外の音にも気づかないのだ。
今日も赤ワインをグラスに注ぎ、一杯だけ飲んだ。遮光カーテンを閉め全ての灯りを消す。
寝るのが楽しくてしょうがない。また紗綾に逢えるのだ。そうだ、あのブラックホールの事を訊いてみなくちゃ。
僕は眠りに就いた。