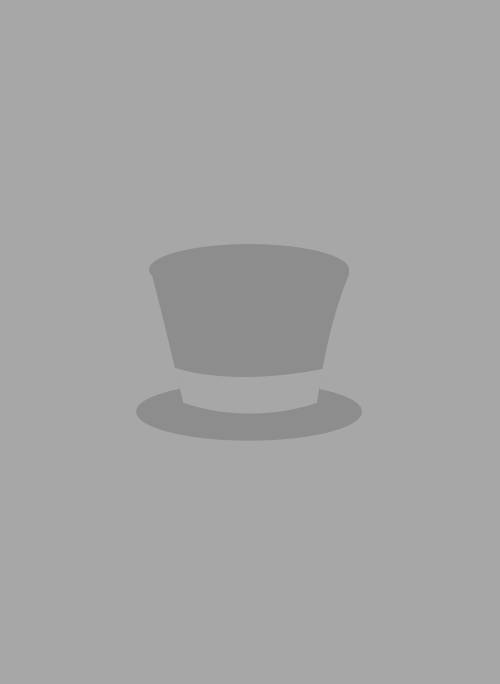ぶつかってしまった彼女――背中に広がる漆黒の髪、陶磁器のように白い肌。
白のドミノマスクがあるとはいえ、二人の容姿はあまりにも酷似していた。
「恵理夜様が二人いるのかと思ったくらいでした」
しかし、恵理夜は彼女と自分との決定的な違いを感じていた。
「とても素直で、可愛らしい人だったわ」
痛みを素直に表に出し、少年が現れたときの安堵の笑顔、申し訳無さそうに謝る表情まで――自分の内側の感情を素直に表現している。
そして、庇護されるべき無垢さを持っていた。
主人の非礼を詫びるためとはいえ、春樹ですら先に彼女へハンカチを差し出したのだ。
何より、あの美しく引き付けられるような微笑みが忘れられない。
恵理夜が持つことのないもの――その嫉妬に似た羨望が胸を焼いた。
白のドミノマスクがあるとはいえ、二人の容姿はあまりにも酷似していた。
「恵理夜様が二人いるのかと思ったくらいでした」
しかし、恵理夜は彼女と自分との決定的な違いを感じていた。
「とても素直で、可愛らしい人だったわ」
痛みを素直に表に出し、少年が現れたときの安堵の笑顔、申し訳無さそうに謝る表情まで――自分の内側の感情を素直に表現している。
そして、庇護されるべき無垢さを持っていた。
主人の非礼を詫びるためとはいえ、春樹ですら先に彼女へハンカチを差し出したのだ。
何より、あの美しく引き付けられるような微笑みが忘れられない。
恵理夜が持つことのないもの――その嫉妬に似た羨望が胸を焼いた。