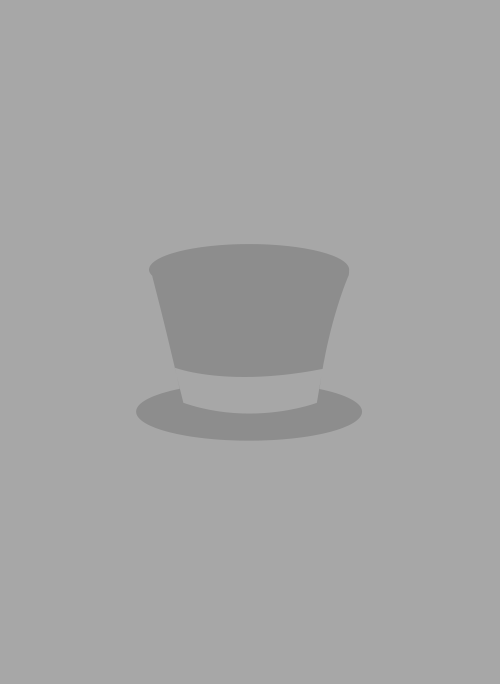「奏。確かに奏の過去は俺が想像も出来ない壮絶なものだったかもしれない。
でも・・・きっと俺みたいにお前の音に感動していた人もいた。
奏は--素晴らしいピアニストだ」
優しい顔つきをする鈴宮は嘘をついているようには見えない。
するとハラハラと涙が零れた。
複雑な気持ちだけど・・・
鈴宮の言葉が素直に嬉しかった。
私のピアノを認めてくれた人がいたんだ。
私は涙を拭った。
鈴宮の言い分も、気持ちもよくわかった。
転校してまで私を追ってきたんだ。
でも・・・
「それでも…私は・・ピアノは弾けない」
私はグッと自分の制服を握った。
でも・・・きっと俺みたいにお前の音に感動していた人もいた。
奏は--素晴らしいピアニストだ」
優しい顔つきをする鈴宮は嘘をついているようには見えない。
するとハラハラと涙が零れた。
複雑な気持ちだけど・・・
鈴宮の言葉が素直に嬉しかった。
私のピアノを認めてくれた人がいたんだ。
私は涙を拭った。
鈴宮の言い分も、気持ちもよくわかった。
転校してまで私を追ってきたんだ。
でも・・・
「それでも…私は・・ピアノは弾けない」
私はグッと自分の制服を握った。