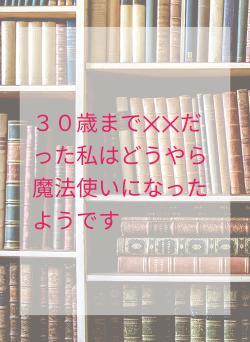小さな六畳一間のアパートで、バースデーケーキもなく、豪華な飾りつけもない。
けれど、ここで迎える3年目の誕生日だった。
特別なものは何一つないけれど、何もない日常が奈々子にとっても冬我にとっても、一番大切なものだった。
当たり前の生活を、当たり前に手に入れることができなかった幼少期。
親という存在にどれほど恋焦がれても、その存在がどんなものかもわからないから、想像することさえできなかった。
浮かんでは消え、浮かんでは消える「家族」の想像図。
その想像は虚しいほどに薄っぺらく、悲しいくらい幼かった。