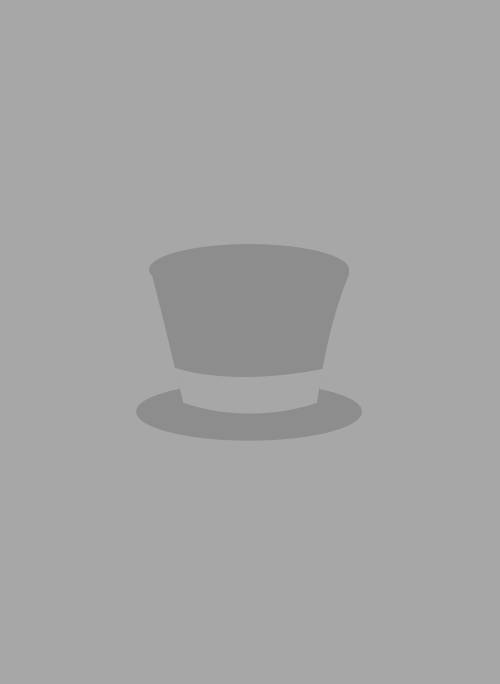「いやしかしだね」
「噂だけならなんとでも言えます」
「実際、緒方先生が葉野に目をかけているのは事実なんだ」
「それは彼女が優秀な教え子だからです」
達郎は失礼しますと言ってきびすを返した。
達郎は葉野亜季が緒方教授とただならぬ関係になっているとは思えなかった。
否、思いたくなかったと言うべきか。
達郎自身、亜季に特別な感情を抱いていることは自覚していた。
『似ているんだ』
達郎は亜季に亡き母の面影を見ていた。
母が亡くなったのは10年以上も前の話。
その時の母の年齢は亜季よりもだいぶ上だったが、それにしてはよく似ていると思った。
若い頃の母の顔はアルバムで目にしていたから、そのイメージが重なったかもしれない。
目鼻立ちだけでなく、全体的な印象も記憶の中にある母と似ていた。
そんな彼女が今日中の解決を望むならそれに応えよう。
達郎は足早に研究棟へと向かった。
「噂だけならなんとでも言えます」
「実際、緒方先生が葉野に目をかけているのは事実なんだ」
「それは彼女が優秀な教え子だからです」
達郎は失礼しますと言ってきびすを返した。
達郎は葉野亜季が緒方教授とただならぬ関係になっているとは思えなかった。
否、思いたくなかったと言うべきか。
達郎自身、亜季に特別な感情を抱いていることは自覚していた。
『似ているんだ』
達郎は亜季に亡き母の面影を見ていた。
母が亡くなったのは10年以上も前の話。
その時の母の年齢は亜季よりもだいぶ上だったが、それにしてはよく似ていると思った。
若い頃の母の顔はアルバムで目にしていたから、そのイメージが重なったかもしれない。
目鼻立ちだけでなく、全体的な印象も記憶の中にある母と似ていた。
そんな彼女が今日中の解決を望むならそれに応えよう。
達郎は足早に研究棟へと向かった。