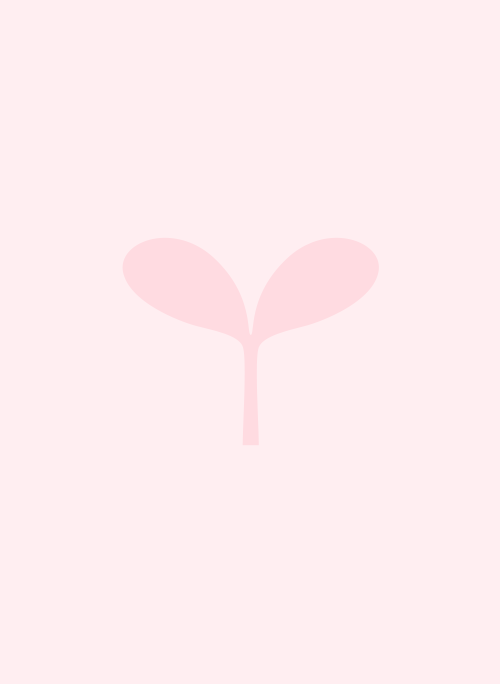円士郎の訪問が一度、二度と重なり──
何物にもとらわれないような彼の奔放さに、私が強く惹かれ始めていた頃、
私は久しぶりに実家に呼び出されて、雨宮の屋敷に戻っていた。
「お前は今年、幾つになったね?」
親戚一同が顔をつき合わせて待ち構える中、
何の話かと薄々想像しながら座った私に、開口一番尋ねたのは叔父だった。
「二十歳ですが」
「そう、二十歳だ」
私の答えに、隠居の叔父は重々しく頷いて、
「二十歳にもなった武家の女が──嫁にも行かず、完全に生き遅れて──
いついつまでも、そんな娘のような格好で、みっともない」
未だ独り身の娘の格好をした私を眺めて、予想通りの言葉を口にした。
二十歳の独身女に対して、「生き遅れる」という表現は諸君らの二十一世紀には考えられないだろうが──
我々の生きるのは、人生五十年の時代だ。
二十歳と言えば、既にその四十パーセントが経過している年齢ということになる。
仮に諸君らの感覚で、人生が八十年とするならば
その四十パーセント──つまり二十一世紀で言うところの三十二才くらいに当たるというところだろうか。
しかし世間の風当たりは、
二十一世紀の三十二才の独身女性に対してよりも、遙かに厳しかったと考えてほしい。
何しろ十五、六で嫁ぐのが当たり前の世の中だ。
と言っても、一年の長さが違うワケでもなし。
人生後半の老後というものはバッサリ存在しないとしても、
私が諸君らの時代の若者たちと同じ二十歳であることは変わらない。
市井の生活は面白く、私はまだまだ今のまま楽しんでいたいと思うようになってしまっていたし、
叔父やここに集まっている親戚連中のように、自分の現状を悲観的には捉えていなかった。
故に──叔父のセリフにはカチンときた。
何物にもとらわれないような彼の奔放さに、私が強く惹かれ始めていた頃、
私は久しぶりに実家に呼び出されて、雨宮の屋敷に戻っていた。
「お前は今年、幾つになったね?」
親戚一同が顔をつき合わせて待ち構える中、
何の話かと薄々想像しながら座った私に、開口一番尋ねたのは叔父だった。
「二十歳ですが」
「そう、二十歳だ」
私の答えに、隠居の叔父は重々しく頷いて、
「二十歳にもなった武家の女が──嫁にも行かず、完全に生き遅れて──
いついつまでも、そんな娘のような格好で、みっともない」
未だ独り身の娘の格好をした私を眺めて、予想通りの言葉を口にした。
二十歳の独身女に対して、「生き遅れる」という表現は諸君らの二十一世紀には考えられないだろうが──
我々の生きるのは、人生五十年の時代だ。
二十歳と言えば、既にその四十パーセントが経過している年齢ということになる。
仮に諸君らの感覚で、人生が八十年とするならば
その四十パーセント──つまり二十一世紀で言うところの三十二才くらいに当たるというところだろうか。
しかし世間の風当たりは、
二十一世紀の三十二才の独身女性に対してよりも、遙かに厳しかったと考えてほしい。
何しろ十五、六で嫁ぐのが当たり前の世の中だ。
と言っても、一年の長さが違うワケでもなし。
人生後半の老後というものはバッサリ存在しないとしても、
私が諸君らの時代の若者たちと同じ二十歳であることは変わらない。
市井の生活は面白く、私はまだまだ今のまま楽しんでいたいと思うようになってしまっていたし、
叔父やここに集まっている親戚連中のように、自分の現状を悲観的には捉えていなかった。
故に──叔父のセリフにはカチンときた。