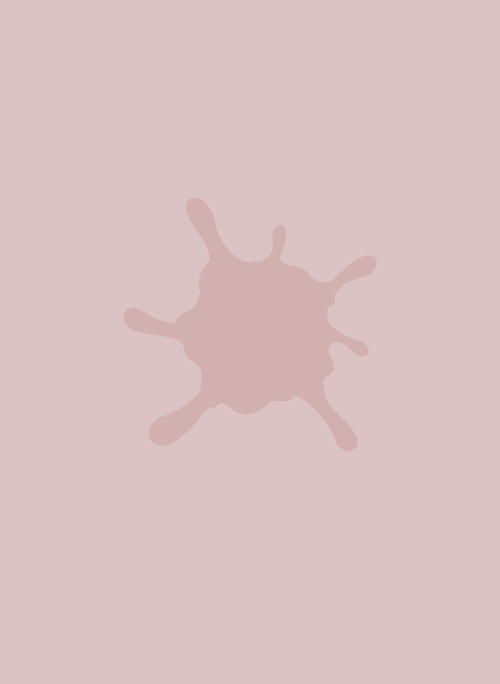予期せぬ問いかけにユゼは一瞬言葉に詰まったようだ。
私は答えを聞く前に続ける。
「あのね。私、長生きすると思うわ。…なんとなくだけど」
昔から病気もあまりせず丈夫で、長生きしそうだといつも言われていた。
自分でもそう思っているし、それが取り柄である。
「だから、貴方が私に飽きて、もう顔も見たくないと思うまで、貴方の花嫁でいてもいいかしら。私なんかでも、いれば少しは気が紛れると思うの。
寝ている間に銀のナイフで刺されても良ければ、の話だけど…」
私は上目にユゼを伺った。勝手なことを、と怒るだろうか。
しかし、最後の冗談が通じたのか、ユゼが柔らかく微笑む。
その笑みに、ああ、こんな顔も出来るんだ、と私は感動したような気持ちになった。
「なら、その時はもう一度私の花嫁になってもらおうか」
言う終わると、ユゼは私の左手を取り、その薬指に唇を寄せる。
誓いの指輪を嵌める、その場所に、ひんやりと冷たい感触が触れた。
「我が花嫁に、永遠の祝福を」
誓うユゼの姿がとても綺麗で、私は他人事のようにぼうっと眺める。
その唇に触れられているのが、自分の指だと自覚した瞬間、顔が赤くなるのを感じた。
「は、離して?」
声が震える。
これはずっと家族でいようという意味なのであって、恋人の誓いではないはずだ。
きっとユゼはそんな風に思っていない。そうに違いない。
だから、こんなことがあっさり出来るのだ。
「なぜ?」
繋がれたままの手が熱を持ってくる。
心底不思議そうにユゼは首を傾げたが、私が本気で困っているのを見ると、静かに手を離した。
なんだか名残惜しいなんて、どうして思うんだろうか。
「わ、私とルーは姉弟で、貴方はそのお父さんじゃ…ないわよね、おじさんってとこかしらっ」
「…はあ」
「だ、だから、家族構成。花嫁になるってことは家族になるってことでしょ。
だから、貴方の私の関係は、おじと姪っ子っ」
「……。……そういう…話だったのか…?」
答えを求めて、ユゼはルーを捜すように辺りを見回したが、もちろんそこにルーの姿はなかった。