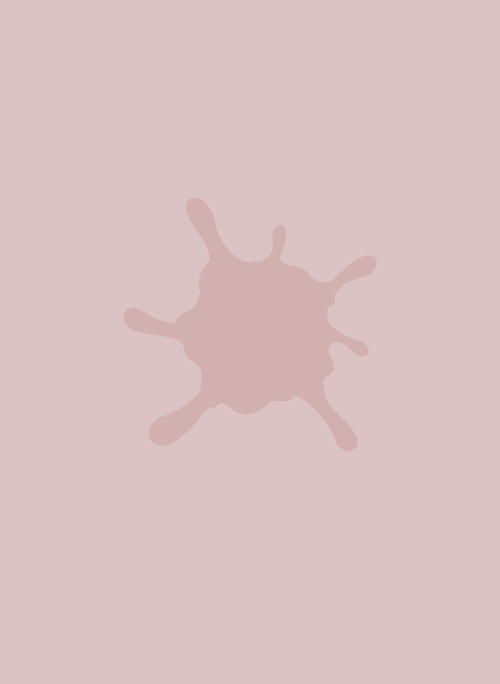ルーも吸血鬼の変化に気付いて、ぴたりと動きを止めた。
「何の真似だ」
「いや、その…吸血鬼に昔を思い出してもらいたいなと思って……」
焦っているルーに冷ややかな視線が注がれている。
「それで」
「そうしたら…あんたが人を好きだったことも思い出すんじゃないか…って…」
「…………」
「花嫁との生活ももっと楽しくなるわけだし…」
ルーの言い分を聞き終えた吸血鬼は、表情を一つも動かさなかった。
「私にとってあの頃の記憶は一番不要なものだ」
突き放すように放たれた言葉。ルーの心を氷が刺していく。
「……そんなっ」
あんまりな返答にルーが悲痛な声をあげる。そして、捨てられた子犬のようにうなだれた。
先程までは、あんなに嬉しそうだったのに。
なのに。
「用はこれだけか」
「……そうだよ…」
二人のやり取りに、私は怒りが湧いてくるのを感じた。
ルーがどれほど吸血鬼を思っていたか知っているだけに、腹立しさも倍増する。
「待って」
私は叫ぶ。しかし、吸血鬼は止まることなく部屋から出て行った。
吸血鬼を追って私も扉の外へ出る。
「待ちなさい」
なんとか追い付いて服の端を掴んだ。
足を止めた吸血鬼が煩わしげに私を振り返る。
「どうして、ルーにあんな言い方するの。ルーはあなたのことを思って」
「お前には関係のない話だ」
私の訴えは一刀両断される。その頑なさに、頭がかっと熱くなった。
「……なくないわ」
吸血鬼の胸倉を掴み、私の方へ引き寄せる。
突然のことに、されるがまま前屈みになった吸血鬼の唇へ私は食らいついた。
ガリッ。
噛み付いた唇が切れる。
傷口から生暖かい血が流れた。
私はその血を舐めとる。
体内にゆっくりと血が混じっていった。一滴では足りないと体が騒ぐ。
それを制して、私は吸血鬼と対峙した。
アイスブルーの瞳が驚きで見開かれている。
忘れているなら、思い出させればいいのだ。
「私はあなたの花嫁なのよ」