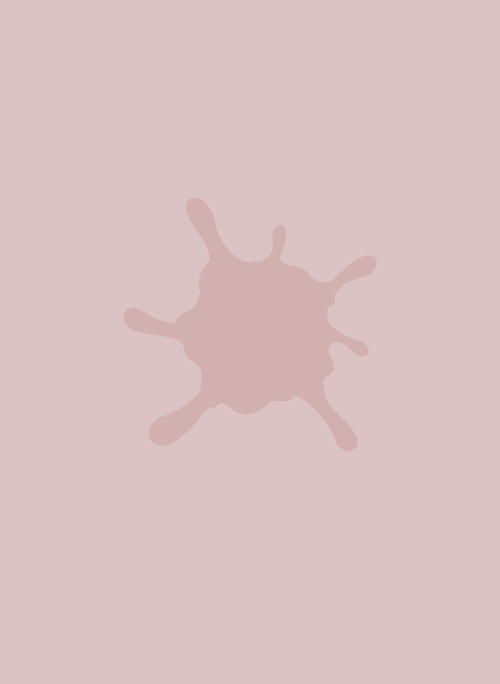だから、ルーは悩むのだろう。
体はいつまで経っても心に追いつけず置いていかれる、その不安定さに。
「何でも出来ちゃうってわけじゃないのね」
「人としての限界って奴だな。吸血鬼は本人も言ってたけど、そういう感覚が生れつき俺たちとはまるっと違うらしい」
「そうなの」
姿形はあまり差異がないのに、細かなところは別の生き物なのだ。
私は布にハサミを入れ、線にそって切っていく。手持ち無沙汰なルーは飾り用の花を玩んでいた。
「強いうえに長生きだから、自然に生まれる数も少ないし、自分たちだけじゃ人のように繁殖出来ないんじゃないかって」
「……そういえば簡単に増やせる割に少ないわよね、吸血鬼って」
考えようによっては、人の子一人を育てるよりも、育った子を吸血鬼にしてしまう方が早い。
吸血鬼がたくさん増えてほしいわけじゃないけれど。
「この国は特に少ないけどな。まぁでも、それは単純に考えて、食料より食べる者が多かったら困るからだろ。人より吸血鬼が多かったら、吸血鬼は共食いか、飢えて滅びるしかない」
言われてみればそうだ。私はあっさりと納得する。
それにしても、自分を食料として見ている生き物がいる、というのは気分のいい話ではない。
私はそのままルーに愚痴る。
「人だって一緒だろ。動物だって人に食べられたいです、なんて思ってるわけねぇんだから。吸血鬼と付き合っていくならそこんとこが重要だ」
意外にもルーは私に同意せず、淡白な言い分をした。
「それは…仕方がないから大人しく血や生気を与えろってこと?」
「いや、あっちにもあっちの事情があるってこと。食べようとする奴の手を引っかくのは食べられる側の権利だろうし」
ルーの言うことは時々難しい。十四歳ではないのだと実感する。
「……引っかいてもいいのかしら」
吸血鬼を。
私は無意識に呟いていた。吸血鬼、というところはかろうじて胸の内に留めておく。
あの時のことは、私から言い出したのだから、怒るのは筋違いだ。
そんなことは分かっている。
なのに、私の心が曇っているのは、心のどこかで吸血鬼の反応のなさに拗ねているのかもしれなかった。