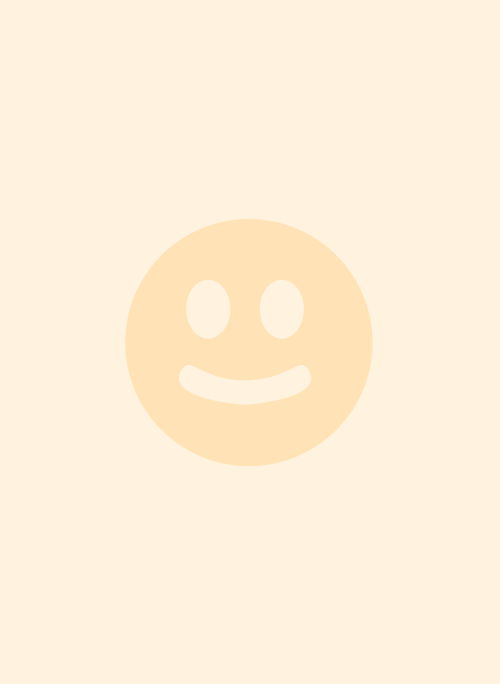「ちょっとちょっと、アヤったら知り合いだったんだ」
窓を閉めたあとも、ランの声は上ずっていた。
「知り合いってほどじゃないし」
「だって、彼の方はちゃんと覚えてたじゃん。ねえ、どんな猫だったの?」
はあ?
猫ってさあ…裸の雌猫だなんて言えるわけないじゃんね。
そんなこと言ったら、私が覗き見してたって言ってるようなものだし。
「きれいな猫だったよ。若い雌猫」
そう。
確かに彼女はきれいだった。
しなやかに体をくねらせ、彼の体にしがみつき、それはそれは美しい雌猫。
「なんだって、メスかどうかまでわかるのよ」
ランは納得がいかないみたいだったけど、私はそのまんま寝たふりをした。
窓を閉めたあとも、ランの声は上ずっていた。
「知り合いってほどじゃないし」
「だって、彼の方はちゃんと覚えてたじゃん。ねえ、どんな猫だったの?」
はあ?
猫ってさあ…裸の雌猫だなんて言えるわけないじゃんね。
そんなこと言ったら、私が覗き見してたって言ってるようなものだし。
「きれいな猫だったよ。若い雌猫」
そう。
確かに彼女はきれいだった。
しなやかに体をくねらせ、彼の体にしがみつき、それはそれは美しい雌猫。
「なんだって、メスかどうかまでわかるのよ」
ランは納得がいかないみたいだったけど、私はそのまんま寝たふりをした。