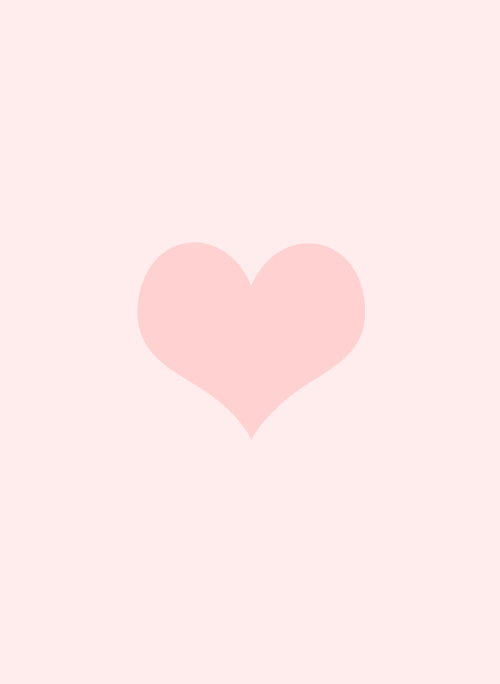「…なんか、ごめんね」
一部始終を見ていた彼が、申し訳なさそうに謝ってきた。
神田くんは何も悪くないため、首を横に振って否定する。
「か、神田くんのせいじゃ、ないから…それで、話って何?」
あれから、神田くんとは一週間以上も話していないため、少し緊張してしまう。
けれど、できれば早くこの場を去りたい。
彼とふたりきりになるのは危険だと、この前のことで十分にわかったから。
「待って、見てあれ…」
「ほんとだ、嘘じゃなかったの?」
その時、廊下を通る同じ学年の子たちが、私たちを見て何やら話し始めた。
そうだ、ここはみんなが通る場所。
つまり目立って当然だ。
そのため神田くんと一緒にいることに対し、さらに危機感を持ってしまう。
慌てて周りを見渡しても、目立たない場所なんてない。