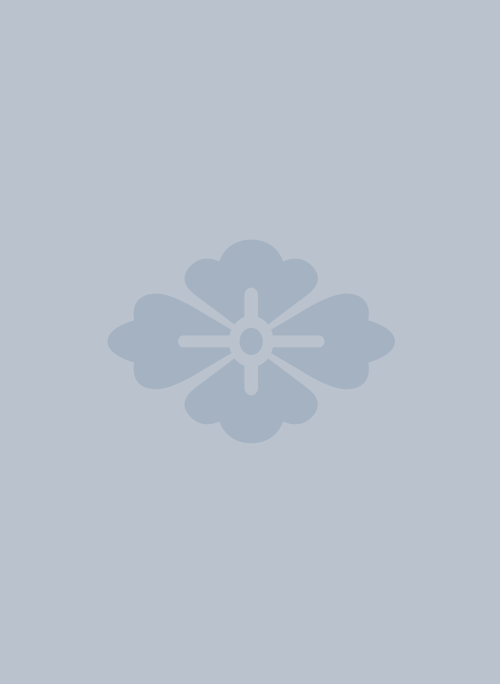それから、半月もしない間にまた彼の所から便りが届いた。
あの時に彼と話ができたのは半刻ほどだった。
私自身はまだまだ話し足りない気持ちでいっぱいだったが、四半刻を超えた当たりから彼が度々退席するように催促してくるので流石にそれ以上は居られなかった。
彼の患う結核は他人に移るもので、恐らくそれを心配してくれたのだろう。
初めは私も大丈夫だからと言っていたが余り聞き入れてはくれなかったようだ。
半刻で話せた事は少ない。
お互いの知らない約五年の月日をたったそれだけで語れる訳がなかった。
特に彼の歩んできた道は尚更。
それでもあった事を掻い摘みながら話してくれて、何と無く、京に居る姿を想像することが出来た。
あっという間で、だけども濃密な時間。
別れ際になるとこのまま時間が止まってずっと一緒に居れればいいのになんて思ったりして、それでも可愛くまだ帰りたくないなんて言えるほど若くもなくて。
大人しく帰り支度を始めた時に、彼が口を開いた。
「あ、そうだ。今度来る時は事前に教えて下さいね。今日は突然で何のおもてなしも出来なかったから」
そんな彼を見て、私はくすりと喉を鳴らした。
「そんなこと気にしなくていいのに」
そう言えば彼も優しく笑ってくれ、そんな姿を見ながらまたねと言って部屋を出た。
この時の私はきっと浮かれていたのだろう。
別れて家に帰る途中、次はいつ来ようかだなんて考えいたのだから。
届いた便りは彼の死を知らせるものだった。