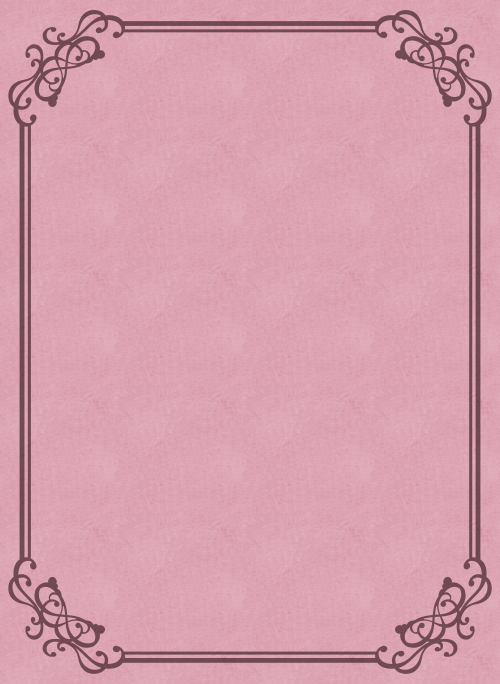あの時、ディアヌの心臓に突き立てられようとした刃。それを阻んだ言葉も完全に嘘だった。そうでなければ、ヒューゲル侯爵は、確実にディアヌを殺していただろう。
その裏にあった想いを、ルディガーはなんとなくわかるような気がしていた。
おそらく、トレドリオ王に対する親愛の情に尊敬の念。さらには、ブランシュに対し、もう一歩踏み込んだ何らかの感情を持ち合わせたということなのだろう。もちろん、それに対し、何か言うつもりもないけれど。
「冗談じゃないですよ。あなたがいなくなるなんて……」
「——俺だって、人間だぞ。いつ死ぬかはわからん」
「何言ってるんですか。民を欺き、後世の歴史を欺き、神まで欺こうという人が——よろしいでしょう。あなたの願い、私が生きている間は、お受けしますが」
ノエルの言葉にルディガーは破顔した。
「お前なら、そう言ってくれると思っていた。これで、安心できるな」
民を欺き、後世の歴史を欺き、神まで欺く。その罪は、どこまでも背負っていく。
彼のために、父や異母兄の——ディアヌ自身は、血のつながりはなかったと思っているわけだが——業をすべて背負って、一人で悪名を背負おうとしていた彼女を守るためならばなんだってする。
「ヒューゲル侯爵も、今後は立場が変わっていくでしょうしね」
「ああ、そうだな。裏切者から、王妃を守ろうとした忠臣だ——今後は、ディアヌの後見人でもある」
結局、ディアヌは『サビーネ王女である』ということになってからも、ディアヌと名乗ることを選んだ。これが、自分の生きてきた証であるからと。
いずれにしても、とルディガーは思う。一番、大切なものを手中におさめることには成功したのだ。