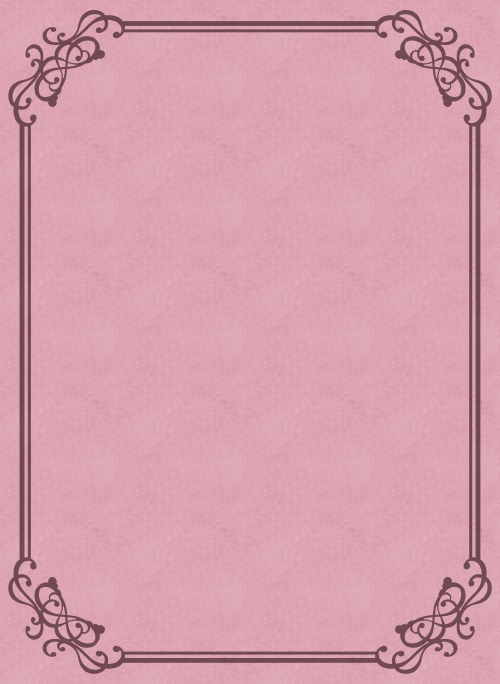「お前の育った場所を破壊するというのがその目的の一つだろうな。今でも、修道院を大切に思っているだろう。それに——ラマティーヌ修道院の人達は、俺の命の恩人でもある」
「……そんな」
「お前が絵図を持ち出さなければ、負けなかった、という思いもあるのだろうな。あの絵図がなかったところで、シュールリトン王家の滅亡は近かったと思うが——」
「私のせい、ということですね……」
ディアヌは視線を落とした。胸の前で組み合わせた両手を強く握りしめる。
間違ったことをしたとは思わない——けれど。
まさか、異母兄の恨みの気持ちが、修道院にまで及ぶとは思わなかったのだ。
「あなただけのせいじゃない。ラマティーヌ修道院は、守りに適した場所だから。あの場所を拠点に、陛下を近くまでおびき出すつもりだろう」
珍しくノエルがディアヌを擁護するような言葉を口にした。彼の目にも擁護が必要なほど落ち込んだように見えたのだろうか。
「そうだな。適当な村を占領し、俺が出てこねば焼き払う。住民は皆殺し——そう言われれば、出ていかざるをえないだろうな。まだ、俺はこの国を完全に受け入れられたとは言えないから」
「そんな、そんな、そんな……」
同じ言葉を繰り返すことしかできない。どうして、こんなことになってしまったのだろう。
「あなたのせいじゃない。他に方法がなかったとまでは言わないが、あなたが懸命に考えた結果だ。孫も、あなたを支持することを選んだのだから」