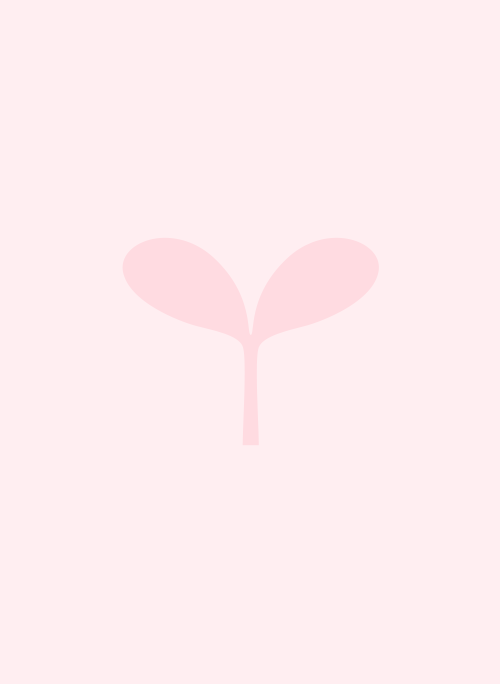「菜音も、読み書きは不得手でしたから」
恵孝の呟きは書物に吸われて消えた。丹祢は手燭を持たずに書架の間を通り抜けていく。
「何か言ったかい。ほら、早くおいで」
闇の中から呼ばれる。恵孝は慌てて後を追った。
「婆様」
「ここだよ」
丹祢の姿を見失ったと思ったら、祖母は床に膝をついているらしい。恵孝も倣って腰を下ろす。
「ここに、地下庫への入口があるだろう」
あるだろう、と言われても、光源のない中で恵孝に見えるのは暗闇ばかり。
「ほら」
手を掴まれて、指先に触れたのは冷たい金具だ。
「取っ手だよ」
思い出した――幼い頃にこれを見つけて、奥に何があるのだろうと思い、開けようとしたっけ。恵孝の記憶の引き出しに、一筋の光が入った。
「開けてごらん。この填め板を持ち上げると、階段になっている」
「何が」
「その先も書物の山だよ。そこでお前に一つ昔話を聴かせようと思ってね。さあ、私じゃ腰を壊してしまうよ」
恵孝の呟きは書物に吸われて消えた。丹祢は手燭を持たずに書架の間を通り抜けていく。
「何か言ったかい。ほら、早くおいで」
闇の中から呼ばれる。恵孝は慌てて後を追った。
「婆様」
「ここだよ」
丹祢の姿を見失ったと思ったら、祖母は床に膝をついているらしい。恵孝も倣って腰を下ろす。
「ここに、地下庫への入口があるだろう」
あるだろう、と言われても、光源のない中で恵孝に見えるのは暗闇ばかり。
「ほら」
手を掴まれて、指先に触れたのは冷たい金具だ。
「取っ手だよ」
思い出した――幼い頃にこれを見つけて、奥に何があるのだろうと思い、開けようとしたっけ。恵孝の記憶の引き出しに、一筋の光が入った。
「開けてごらん。この填め板を持ち上げると、階段になっている」
「何が」
「その先も書物の山だよ。そこでお前に一つ昔話を聴かせようと思ってね。さあ、私じゃ腰を壊してしまうよ」