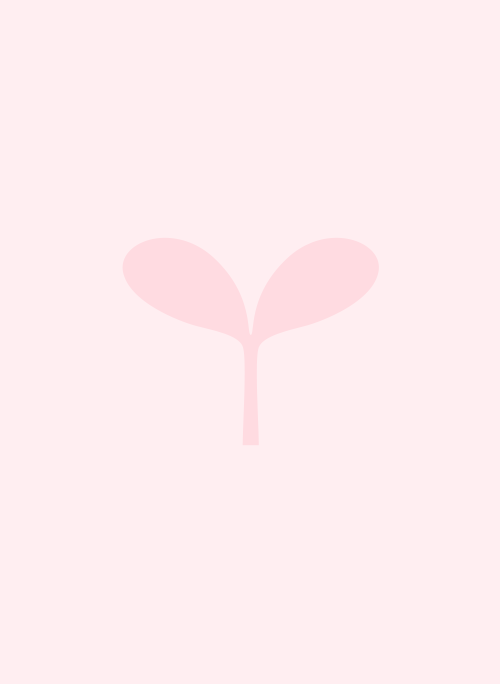恵孝も自室に戻ろうと立ち上がり、部屋を出た。
「恵孝」
出たところで祖母と会った。手燭を提げ、丹祢はじっと恵孝の目を見る。父の目は祖母譲りだ、と恵孝は改めて思った。
「何ですか」
祖母は口元を緩ませた。
「今晩は、母さんの傍についていておやり。富幸の支えはお前なのだよ」
そして、手にしていた上着を恵孝に持たせた。自分は踵を返して行く。寝室とは違う方へ向かう祖母の背が夜の闇に消えたのを見て、恵孝も戻った。
「母さん」
祖母に託された上着を母の肩にかけ、その隣に座る。恵孝が差し述べた手を富幸は両手で掴み、そこに額を乗せた。祈りを捧げるようだった。
夜が更けていく。
夕方は明日の快晴を示すような美しい夕焼け空だった。十六夜の月は、夜空を青白く照らしているだろう。
昨夜の雨がなければ。
こんな長い一日は訪れなかったのに。
「恵孝」
出たところで祖母と会った。手燭を提げ、丹祢はじっと恵孝の目を見る。父の目は祖母譲りだ、と恵孝は改めて思った。
「何ですか」
祖母は口元を緩ませた。
「今晩は、母さんの傍についていておやり。富幸の支えはお前なのだよ」
そして、手にしていた上着を恵孝に持たせた。自分は踵を返して行く。寝室とは違う方へ向かう祖母の背が夜の闇に消えたのを見て、恵孝も戻った。
「母さん」
祖母に託された上着を母の肩にかけ、その隣に座る。恵孝が差し述べた手を富幸は両手で掴み、そこに額を乗せた。祈りを捧げるようだった。
夜が更けていく。
夕方は明日の快晴を示すような美しい夕焼け空だった。十六夜の月は、夜空を青白く照らしているだろう。
昨夜の雨がなければ。
こんな長い一日は訪れなかったのに。