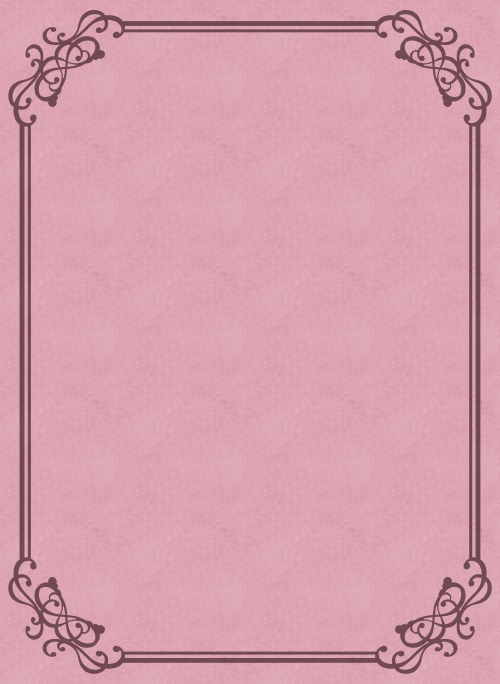信仰の道を歩む者が戦場に立つなんて、本来ならばありえない話なのだが、クラーラ院長は積極的に修道女達を戦場に送り出していた。
——戦い方を忘れてしまっては、近隣で暮らす人々を守ることはできないから。
「あとひと月もしないうちに、都にルディガーの軍は到着するのですって——私達も、そろそろ動き始めなければね」
この城に戻ってきてから知った。
父であるマクシムには、王たる資格などなかった。自分の欲望のために民を苦しめ、それで平気な顔をしている。
城内に重苦しい空気が漂っているのも、いつの間にか当たり前のこととなっていた。
「……散歩に行きます。供をしなさい」
「かしこまりました、姫様」
十六になった今も、ディアヌが側に置くのはジゼルだけだ。今は二十を過ぎたジゼルだけれど、あいかわらずディアヌの側に付き添ってくれる。彼女がいなければ、きっとここまで来ることはできなかった。
ジゼルと並んでディアヌは廊下を進む。彼女が身に着けているのは、飾り気の少ない簡素なドレスだった。宝石類も身に着けていない。
年頃になった娘とは思えないほどの質素さだった。
廊下を歩みながら、ディアヌはつぶやいた。
「……どんどん人が逃げ出しているような気がするわ」
かつては栄華を誇っていたのだろう。二年前、この城に来た時にはもう少し多数の人間がいたはずだ。
だが、今はそのにぎやかさも失われてしまっている。王を恐れ、王子を恐れ、使用人達はどんどん逃げるようにやめていった。