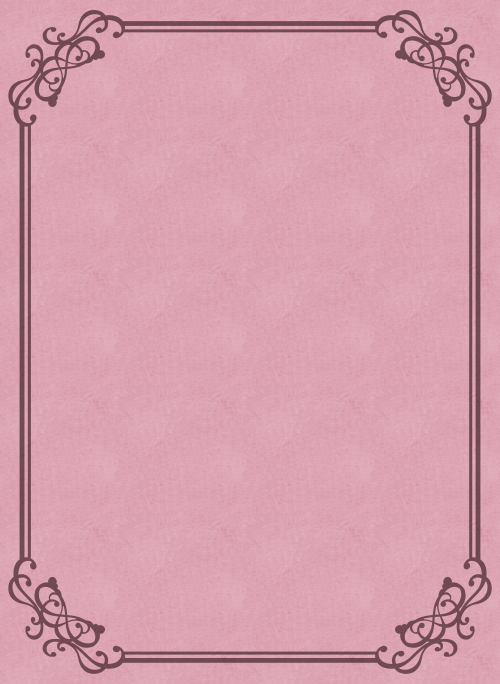なぜ、とルディガーがつぶやいた。そんな彼の方へ、クラーラは血糊をぬぐった剣を差し出す。
「私は傭兵だから、雇われればどこでも働いた。あなたの父親のもとでも働いたことがあるよ——あなたの父は、立派な男だった」
それを聞いて、ルディガーは目を丸くした。
ルディガーが、ただの兵士ではなく、セヴラン王家の血を引く者だと、この時初めてディアヌは知った。
「……俺をマクシムに引き渡さないのか」
「セヴラン王家の者を引き渡せなんて依頼にないからね。私達は、依頼されないことは引き受けない——私が依頼されたのは、ディアヌ姫様をここでお守りすることだけ。トレドリオ王妃、ブランシュ様の依頼で」
どうして、院長はディアヌの素性をルディガーに教えてしまったのだろう。ディアヌの素性は、誰にも明かしてはいけない。修道院に身を寄せる貴族の娘で押し通す様にと言い含めてきたのは、院長なのに。
「トレドリオ王妃——だが、マクシムの娘だろう」
「そうだね。でも、あの男の元に、ご自分の腹を痛めた娘を置いておきたくないというのがブランシュ様の願いだから。さ、さっさと荷物をまとめて出ていきなさい。うちの修道院の者に、そこまで送らせるから」
目の前でてきぱきと物事が決められていく。
「ルディガー、本当に行っちゃうの?」
もう少し、彼と一緒にいたかった。けれど、それはもう許されない。
(……セヴラン王家って、お父様の敵だから)
もし、ディアヌがシュールリトン王家の娘ではなかったら、ルディガーはもう少しだけここにいてくれただろうか。
「いつか、もう一度会いに来るよ。その時には——お前を解放してやるから」
約束の印は、額に落とされた優しいキス。
それから五年以上の間、ディアヌがルディガーの名前を聞くことはなく——再び彼の名を聞いた時には、彼の言う『解放』の意味を理解し始めていた。