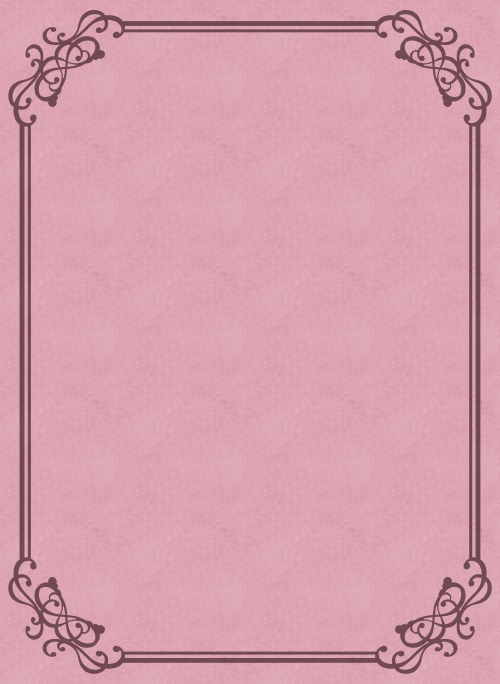「ということは、後ろの赤毛はジゼルか」
「赤毛って——」
また、ジゼルを手で制する。今は、そんなことをしている時間も惜しい。
「私の願いを聞いていただけますか、陛下?」
できるだけ、堂々として見えればいい。できる限り大きく見せようとわずかに背をそらす。
「聞くだけなら」
「わが父マクシムの死——そして、今のシュールリトン王家の滅亡を」
父と一族の滅亡を願うディアヌの言葉に、室内がわずかにざわついた。
「それは俺もなんとかしたいと思っているが、なかなか難しい。ノエルの話では、それを現実にする方法を持ってきてくれたとか?」
ノエルというのは、ここまでディアヌとジゼルを案内してくれた男の名前らしい。彼の手には、ジゼルの剣がある。
「人払いをお願いはできませんか?」
「それは無理だ。わが王と敵国の王女を二人きりにできるはずないだろう?」
話を聞いてくれるところまでは、想定していたのだが——さすがに、二人きりというのは無理か。
誰に見つかっても困らないよう、隠してきたものをこの場で取り出すのはためらいがある。
ディアヌは肩を揺らしたけれど、数度大きく呼吸して腹を決めた。
「……しかたありませんね」
「姫様!」
ジゼルの叱責する声も聞こえていないようにディアヌは自分のマントに手をかける。脱いだそれをジゼルに渡す。
何か言いたげな彼女には、首を横に振ってそれ以上の言葉を封じた。