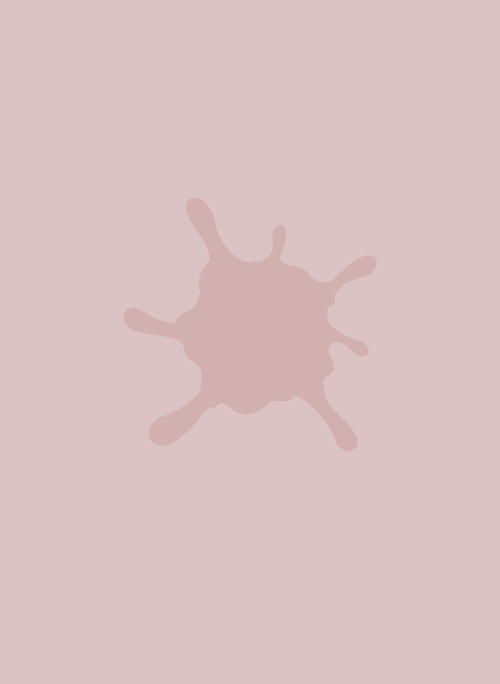「特に必要ないって言ってるのに毎日やってこられたら、そりゃ無愛想にもなるんじゃない?」
少しだけ意地悪してやるか。
そんな気持ちが湧き上がり、僕はちょっとだけ笑みを作ってみせる。
僕のその言葉に、彼女は「うっ」とうめいて見せた後、大袈裟に胸を押さえてみせる。
「ひどいなぁ、引きこもってる鈴木君の為を思ってなのに」
「はいはい、ありがと」
「全然感謝してるように聞こえない」
「そうだね」
適当にあしらってやると、彼女は少しむくれてみせた。
「前だったらそんな意地悪も言わなかったのに」
「そうだったっけ」
とぼけながら、僕は以前の自分を思い出す。
少しだけ意地悪してやるか。
そんな気持ちが湧き上がり、僕はちょっとだけ笑みを作ってみせる。
僕のその言葉に、彼女は「うっ」とうめいて見せた後、大袈裟に胸を押さえてみせる。
「ひどいなぁ、引きこもってる鈴木君の為を思ってなのに」
「はいはい、ありがと」
「全然感謝してるように聞こえない」
「そうだね」
適当にあしらってやると、彼女は少しむくれてみせた。
「前だったらそんな意地悪も言わなかったのに」
「そうだったっけ」
とぼけながら、僕は以前の自分を思い出す。